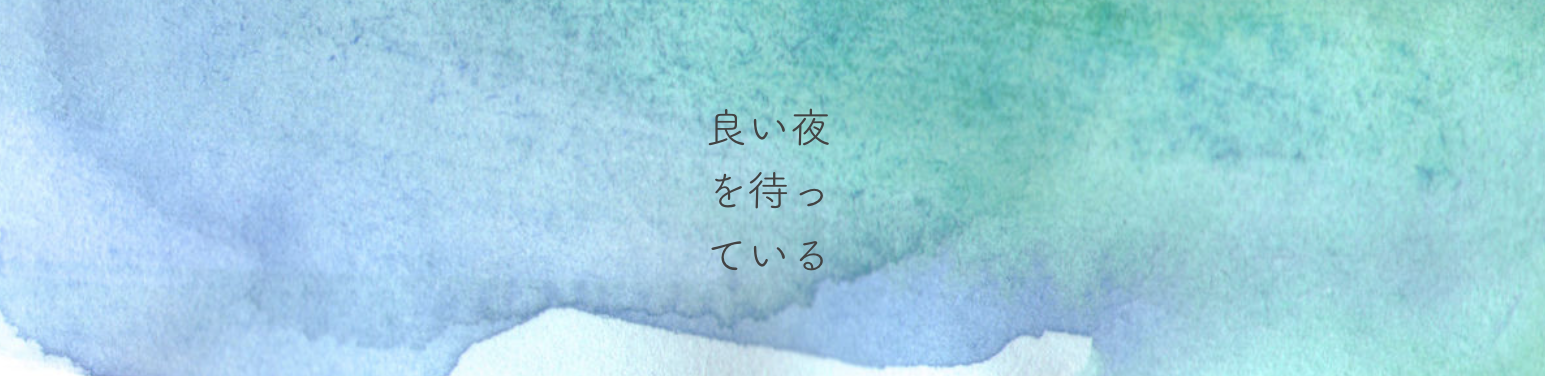本しかなかった。
誇張でも冗談でも自虐でもなんでもなく、単なる事実として、本当に心の支えと呼べるものは、私にとって本、いわゆる文学しかなかった。
本でなくても、絵でも、写真でも、音楽でも、園芸でも、なんでもいい、何かに心を奪われてすべてを持って行かれてしまうような体験をした人は少なくないだろう。そしてそのときの衝撃がどうしても忘れられなくて、だいすきで、ずっとずっと追い求めてしまう。こんなことは無駄かもしれない、わかっている、それでもどうしても、手を伸ばさずにはいられないもの。
私にとって、それは文学だった。文学は、言葉は、それこそ文字通り、ある種の呪いであり、まじないであり、言祝ぎであった。
それしかないこと、読むしかできないことが苦痛を伴わなかったかというと嘘になる。読書は勿論楽しい。楽しいけれど、私の感受性がそのことで豊かになったのかというと疑問が浮かぶし、そこから何か生産しているかというとそうではないし、文学を仕事にしているわけでもない。読書が単なる「消費」にならないように気をつけているけれど、本当に「消費」でないのかと問われると答えに窮する。
それでも、私にとって読書は、もう、単なる趣味以上のものになってしまった。本がないと居ても立ってもいられない、どうしたって手放せない、衣食住の次に必要なもの。なのになぜか、そのことに対して少しばかりの罪悪感と劣等感があった。これでいいのか、分からなかった。ただ好きでいられることを喜べば良いのかもしれない、誇れば良いのかもしれない。でもそれが上手くできなかった。
『ストーナー』を読み始めたとき、私はこの本が、私にとってひとつの分岐点になるような予感がしていた。私の人生に、またひとつ、大切な本が増える。それだけでなく、この物語こそが、私のための物語になりうると、誰のためでもなく私のための物語だと、そう言い切って良いのだと、思えたのだ。
この本のあらすじは物語の冒頭に書かれていることがほぼ全てである。ひとりの冴えない大学助教授ストーナーの、冴えない人生の物語。農家で生まれて、大学に入って、就職して、恋をして結婚をして、働いて、死んでゆく。ただそれだけの物語。派手な事件や激動の瞬間は、はっきりいって、無いに等しい。多少の盛り上がりはあれど、ひとことで言ってしまうと凡庸だ。それでもこの物語がこんなにも胸をうつのは、細部がとんでもなく美しいからに他ならない。
農学部の生徒だったストーナーが、必修でたまたまとった英文学の授業で、シェイクスピアのソネットに魅せられてしまう場面がある。教授であるスローンが、詩を詠じ、ストーナーに問いかける。
「それを見定めたきみの愛はいっそう強いものとなり、
永の別れを告げゆく者を深く愛するだろう」
スローンは視線をウィリアム・ストーナーに戻して、乾いた声で言った。「シェイクスピア氏が三百年の時を越えて。きみに語りかけているのだよ、ストーナー君。聞こえるかね?」
ウィリアム・ストーナーは、自分がしばしのあいだ息を詰めていたことに気づいた。そうっと息を吐き、肺から空気が出ていくにつれて服が少しずつ皮膚の上で動くのを意識する。ストーンから目をそらして、教室内を見回した。窓から射し込んだ陽光が学生たちの顔に降りかかり、あたかも体内から発する灯りが薄闇を照らしているように見えた。ひとりの学生が目をしばたたき、陽射しを浴びたその顔に和毛の細い影が落ちた。机のへりを固く握りしめていたストーナーの指から力が抜けていく。てのひらを下に向け、改めて自分の両手に見入ったストーナーは、その肌の茶色さに、爪が無骨な指先に収まるその精緻なありかたに、感嘆の念を覚えた。見えない末端の静脈、動脈を血が巡り、かすかではかなげな脈動が指先から全身へと伝わっていくのが、感じ取れるような気がした。
p.14-15
周りの学生たちがうめいたりぼやき合ったりしながら席を立ち、退室するのを、ストーナーは気に留めなかった。誰もいなくなってから数分間、じっと坐ったまま、メモ前の狭い板張りの通路を見据える。見も知らぬ無数の学生たちのせわしない足に踏まれて、ニスの膜は剥がれてしまっていた。自分の足を床にすべらせてみると、靴底のこすれる乾いた音がして、ごつごつした感触が足の裏に伝わってきた。それから、ストーナーも立ち上がり、ゆっくりと教室をあとにした。
晩秋のうそ寒さが服の下までしみ通った。ストーナーはあたりを見回し、薄青い空を背にくねくねと立つ木々の節だらけの枝に目を向けた。次の授業へと急ぎ足でキャンパスを横切る学生たちが、そばをかすめて過ぎた。つぶやきの声と敷石を打つかかとの音が聞こえ、微風に向かって前かがみになった顔が冷気で紅潮しているのが目に入った。ストーナーはまるで初めての光景のように、好奇の目で同輩たちを眺め、とても遠くに、なおかつとても近くに感じた。
p.16
素晴らしい文学に触れたとき。その一節が、何もかもを圧倒して迫ってくるとき。突風が正面から吹き付けて私と対象以外のものを全てなぎ倒し、世界が私と対象だけになり、息もできず、闇と静寂に包まれる。そしてそのあと、じわじわと感覚や色、光、音が戻ってくる。この目は間違いなく現実を見ているはずなのに、どこか乖離してしまって、先の衝撃の余韻に浸る自分を内側から、外側から、ぼうとした頭で観察している。
私はこれまで、何度も何度も本を読んでこの体験をした。そして、ストーナー同様、取り憑かれてしまったのだ。文学に、言葉に。
屋根裏部屋で過ごす夜、読んでいる本からときどき目を上げ、ランプの火影が揺れる隅の暗がりに視線を馳せた。長く強く目を凝らしていると、闇が一片の光に結集し、今まで読んでいたものの幻像に変わった。そして、あの日の教室でアーチャー・スローンに話しかけられたときと同じく、自分が時間の流れの外にいるように感じた。過去は闇の墓所から放たれ、死者は棺から起き上がり、過去も死者も現在に流れ込んで生者にまぎれ、そのきわまりの瞬時に、ストーナーは濃密な夢幻に呑み込まれて、取りひしがれ、もはや逃れることはかなわず。逃れる意思もなかった。トリスタンが、金髪のイゾルデが、目の前を歩いていく。パオロとフランチェスカが、身を灼く闇の中を漂っている。ヘレネと王子パリスが、咎を負った苦々しい顔で薄闇から浮かび上がってくる。そういう登場人物たちとストーナーが結んだ絆は、大学の同輩たちとはけっして結ぶことのできないものだった。
p.18
今でこそ全てを忘れて本に没頭することは少なくなったけれど、小さい頃はまさにこの通りだった。夜、ひとりで本を読んでいると、夢も現も時間や空間すら関係なしに彼らは本から飛び出し、 私の周りを漂った。笑い、泣き、さざめく声が聞こえ、行ったこともない場所の風景が現前した。言葉の亡霊たちは、いつも私の前に現れて、私を連れ去ってくれた。
教授スローンは、農学から英文学に転じたストーナーに博士課程への進学と教鞭をとることを勧め、たじろぐストーナーにこう告げる。
「わからないのかね、ストーナー君?まだ自分というものを理解していないのか?きみは教師になるのだよ」
突然、スローンがとても遠くに見え、教官室の壁も遠のいた。ぽっかり広がった空間に宙吊りにされた気がして、そこへ自分の声が聞こえる。「本気の話でしょうか?」
「本気だとも」スローンは穏やかに言った。
「どうしてです?どうして、そんなふうに思われるんです?」
「恋だよ、ストーナー君」興がるような声。「きみは恋をしているのだよ。単純な話だ」
p.23
そう、まさしく、これは「恋」だったのだ。胸が苦しくなり、そのことしか考えられなくなり、何をしていても常に纏わりついてくるあの感じ。離れようとしてもできなくて、苦しいのに何度も読み返してしまう一冊があること。いままで言語化することが(おそらく、怖かったのだ)できなかった文学への気持ちは、こんなに単純なものだったのだ。
「言葉にできないものを言葉を通じて知る」こと、言葉の持つ魔力に惹き寄せられること。私がずっと焦がれていたことが、言葉に出来なかったことが、こんなにも美しく、静かで精緻な筆致で語られていく。どこまでも穏やかに、ときに無骨で生きることに不器用なストーナーの在り方と彼の世界は、大人になって何者にもなれなかった私をまた、もう一度、物語の世界へ連れて行ってくれたのだ。小さいころにいつだって連れて行ってもらえた、何もなくて何もかもがあった、文学の世界をもう一度新たに照らしてくれた。
そして戦争があり、ストーナーは恩師と友人を喪い、恋をして結婚をし、日々を過ごしてゆく。
この本の中では、妻イーディスとの次第にぎくしゃくしてしまう関係や、ストーナーのことを目の敵にする同僚のことも、妻以外の女性との愛の交歓も情愛も官能も、アルコールに溺れてゆく娘のことも、等しく穏やかな目線で描かれる。それらのひとつひとつが、はたから見ると辛くやりきれないことでも、ストーナーは静かに受け止めてゆく。それらのひとつひとつが、淡く滲んだ光を放つように、美しい言葉で綴られてゆく。
美しさ、としか形容できないのだが、こんなにも胸を締め付ける言葉があったのかと、もっとこの言葉たちに触れていたいと祈るようにページをめくることしかできなかった。(本当に、全てにおいて狂おしいほどの美しさなので、ここで全てを引くことは不可能だし、もったいないと思うのでどうかこの記事が、あなたに届くならば、あなたの目で確かめてほしい。特にストーナーが十日間を過ごす冬のコテージの描写は内臓を両手で絞られるような気持ちになる、眩しくて切なくて。)
全篇を通じてこの本には絶望感がある。拭い去れない悲しみや喪失感、そういったものが根底に流れている。理不尽にぶつけられる怒り、どうにもできない戦いのこと。
ストーナーは老いてゆく。身体は動かなくなり、意識も途切れがちになってゆく。すべての人間がそうであるように、生きて、死んでゆく。
ストーナーは何者にもなれなかった。何者でもなかった。思うように事は運ばず、地位も名誉も財産も手に入れられなかった。失うことのほうが多かったかもしれない。
けれども。
彼は不幸だったんだろうか。
ストーナーには、文学があった。初めて心に火を灯した文学を、ずっと大事に、てのひらで包んで守ってきた、きっと彼は意識なんかしなかったんだろう、消えないようにその灯りを守ることは呼吸をするようなものだったんだろう、ときに火傷しそうなほどに激しく燃え、ときにチリチリと音を立てて消えそうになっても、彼はずっと、ずっとその光に向かって手を伸ばし続けた。
彼は不幸だったんだろうか。
その答えはラストの1ページに記されている。静かに、あたたかく窓から射す光のように、ひとつひとつを慈しむような言葉で綴られている。
訳者の東江一紀さんは、この本を病床で、癌と闘いながら、口述筆記を頼みながらも翻訳を続けたという。生涯最後の翻訳としてこの本を選び、最後の1ページを残して亡くなられた。東江さんの訳は、翻訳の素晴らしさを、遠い異国の作品を、時を越えて届けてくれた(『ストーナー』は50年前の作品)。
生きづらさを抱えた、地味でうだつのあがらない主人公の物語を、東江さんは優しく、温かく、こんなにも美しい日本語に訳された。東江さんの最期とストーナーの最期が交差したこの本は、あまりこういう言葉を使うのは気に入らないのだけれど、一種の、奇跡、だったのではないかと思う。
私もきっと、何者にもなれないし、この生きづらさ、息のしづらさを抱えてこの先も生きてゆくのだろう。友達もほとんどいないし、社会とはうまくやれないし、鬱屈とした人生だ。
でも私は、この本に出会えた。本しかなかった、私のことを、ただただ温かく包んでくれた。ただそっとそばに居てくれた。何も語らず、何もかもを語ってくれた。
文学には救いがあると、私は、まだ信じている。
どうか、あなたにもこの物語が届いて、あなたのための物語になりますように。
そして、最後まで読みきったら、本のカバーをめくってみて。