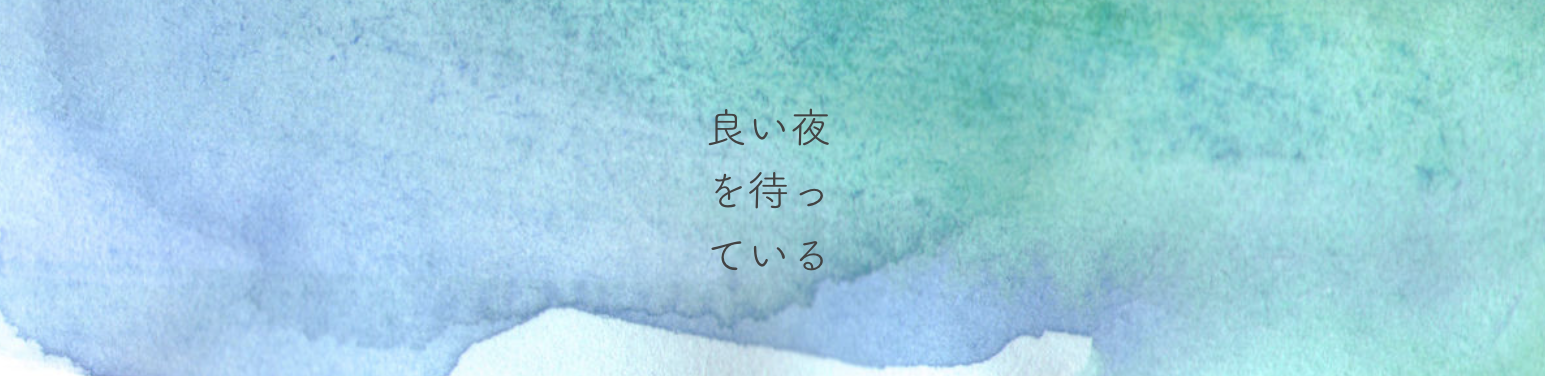長らく絶版になっていたサンリオSF文庫から時を経てちくま文庫から復刊された『氷』。カヴァン生前最後の作品。
SFとも幻想文学ともとれる(プリーストの序文にはスリップストリーム、とある)この作品、のっけから眼前に迫る氷のヴィジョンに圧倒される。
どこも完全に巨大な氷の壁に閉ざされている。眼をくらませる光の爆発に氷は流体となり、壁全体がとどまることのない液体の動きを見せて刻々変容しつつ前進し、海洋ほどにも巨大な雪崩を引き起こしながら進んでいく氷の奔流が、破滅を運命づけられた世界の隅々にまであふれ広がっていく。どこを見ても、少女の眼に映るのは同じ恐るべき氷の環状世界。そそり立つ氷の壁また壁。のしかかってくる猛々しい巨像のような極寒の氷の波が、今まさに少女の頭上で砕けようとしている。氷から放射される死の寒気に凍りつき、氷の結晶の強烈な輝きに視力を奪われて、少女は自身もまたこの極地のヴィジョンの一部になったように感じる。
主人公のある男が、幼少期に母親から虐待を受けたせいで何事にも怯え、隷属的な態度しか取れなくなってしまったアルビノの少女に恋をし、少女を追いかけて氷の世界を旅する、というのが主な筋だが、実に潔くそれ以外の説明がほとんど無い。この世界がどこなのか、時代はいつなのか、なぜ主人公はこんなにも金持ちなのか(諜報員らしき仕事をしているようだが、とにかくじゃんじゃん金を使っている)よくわからない。よくわからないまま、世界は氷に包まれていき、戦争が勃発して情勢も悪化の一途を辿り、緊迫した状況の中、少女は追いかけても追いかけても捕まらない。時折、少女に相まみえる場面もあるが、それが妄想なのかそうでないのかも曖昧なまま、またすぐに捕まえた腕からするりと少女は抜け出し去ってしまう。
世界を徐々に押しつぶしてゆく巨大な氷の研ぎ澄まされたイメージと、白く冷たく、すぐに折れてしまいそうなくらい細くて儚い少女のイメージが相互に作用してキンと張り詰めた空気感の中、その世界観の美しさもさることながら、私がのめり込んだのは、下世話な言い方になってしまうけれど、そのエロさだった。
ゆるやかなカーブを描く長いまつげ、おずおずした魅惑的なほほえみ。次いで、私が意のままに作り出せる様々な表情が浮かぶ。ほほえみが不意に傷ついた表情に変わり、たちまち怯えに、涙に移行してしまう。この誘惑の強さに私は動揺する。振り降ろされる死刑執行人の黒い腕、少女の手首をつかむ私の両手・・・・・この夢が現実に変わるかもしれないことが恐ろしい・・・・・少女の内にある何かが、彼女を犠牲者にすることを要求する。
ようやく、私は瓦礫の間に横たわっている少女の身体に蹴つまずく。異様な角度にねじ曲がった頭。渦巻く煙と土埃を通して、黒い土と建物の残骸を背にした白い肌が見える。その白い肌の上の血は、最初は赤く、やがて黒くなっていく。豊かな銀白色の髪をつかんで横ざまにねじられた頭。折れた細い首。
執拗に繰り返されるつららのような少女の細さと儚さ、少女を愛していながらも(愛しているからこそ)少女を虐げたいという昏い欲望が導き出すヴィジョンと、少女を殺すのは自分しかいないと思い続ける主人公の執念に同調してしまいとにかく読んでいるあいだじゅう、エロい、エロ過ぎる、と思いながら読んでいた。
官能的、というよりなんだかもっと低俗で下世話な感情を抱いてしまった。それがこの世界観によるものなのか少女の外見や立ち居振る舞いによるものなのか、わからないけれど、はじめから終わりまで一貫してエロかった(決してこの作品に書かれている文章は下品ではない、念のため)。
二人はともに少女を苦しめた。少女にはその理由がわからなかった。それでも、これまでみずからの身に起こることすべてを受け入れてきたように、その事実を受け入れた。虐待され、犠牲者にされることを予想しながら。人間の手によってであれ未知の力によってであれ、最終的には破滅に至らしめられることを予想しながら。この運命は時が始まった太初からずっと少女を待ち受けていたように思われた。その運命から少女を救えるものがあるとしたら、それは唯一、愛だけだった。
少女を救おうとし、また同時に少女を恐怖の底に突き落とそうとするアンビバレントな心理を抱えて苦悩し、こんなことは続けていても意味が無い、やめようと何度も試みるけれど、それでもやはり少女を追いかけ続けてしまう主人公が言う「愛」が最終的にどのような結末になったのかはわからない。氷は小説のラストまで世界を覆い尽くすことをやめないし、ハッピーエンドとは決して言えないラストだが、それでも少し救われたような気持ちになるのは、歪んでいても報われなくても世界が終わっても少女を追い求める、主人公の(一途すぎる)愛が感じられたからかも知れない。
解説では川上弘美が文を寄せていて、とても良かったのでご紹介。
「狭い」という言葉は、あまりいい印象を与えないかもしれない。大きな小説、とか、大きな世界、という方が、ずっと「いい」感じがするだろう。でも、カヴァンの「狭さ」は、ほかに類をみない「狭さ」なのだ。その狭い隙間に、体をするっとすべりこませたが最後、もう二度と出られなくなるような。そして、出ようとして、さらに狭い奥へ奥へと進んでゆくと、もう入り口は全然見えなくなっていて、でもその先も見えなくて、絶望してしまうような。絶望してしまったすえに茫然とたたずんでいると、今までに感じたことのない不可思議な心地よさ、がやってくるような、つまりその絶望感は、ある種の官能を刺激するものであるような。
カヴァンの作品は以前に『アサイラム・ピース』(装丁がめちゃくちゃに良い)を読んで、「ほお・・こういうのもあるのか・・・」程度の感想しか抱けなかったのだが、この本はすごい。続々出ているカヴァンの作品の中で唯一(現在絶版になっていない)文庫なので是非手にとっていただきたい。 エロいし。