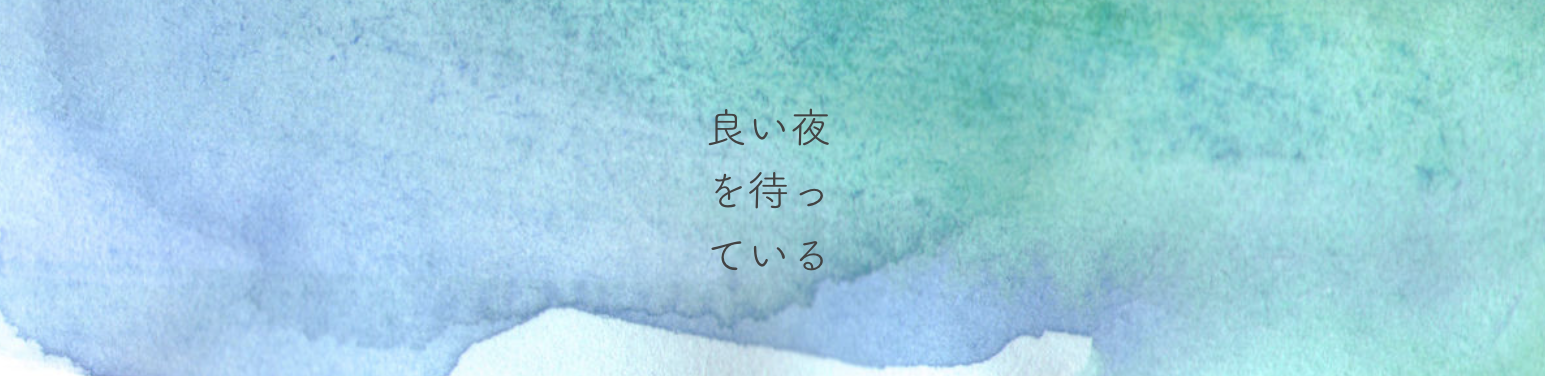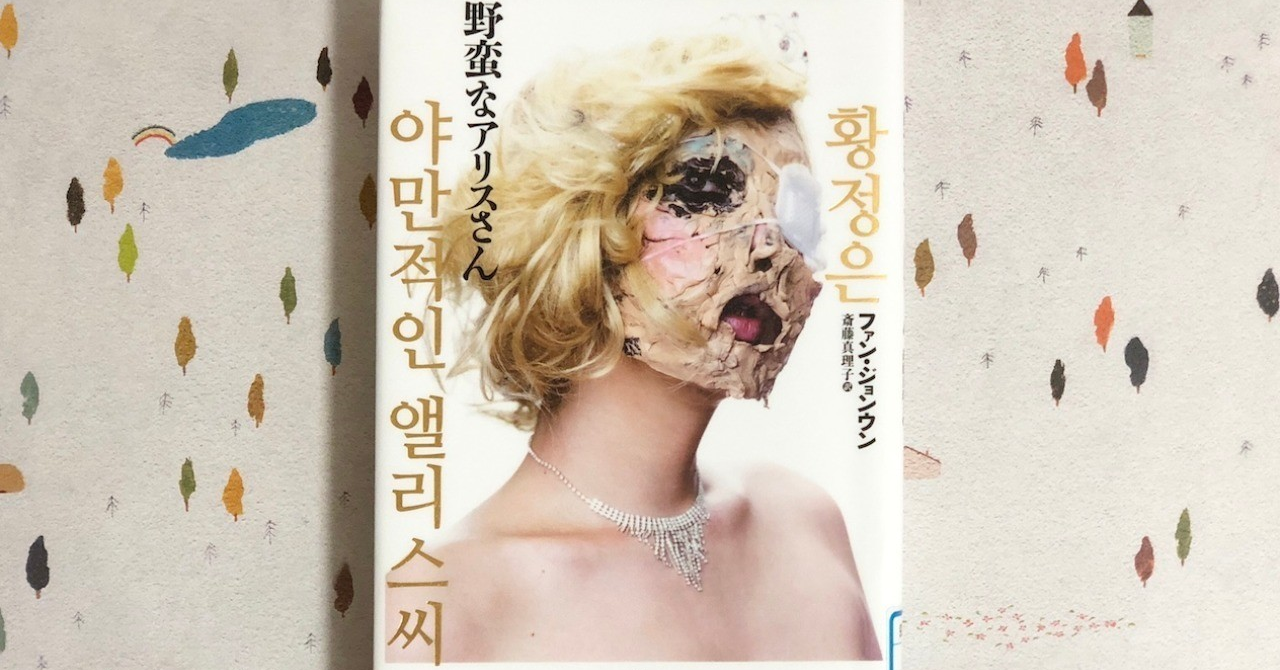
近年の韓国文学の躍進はめざましいものがある。
日本翻訳大賞の第一回と第四回ではそれぞれ『カステラ』と『殺人者の記憶法』が受賞しているし、近現代の作品がどんどこ翻訳されている。この躍進は、今回取り上げるファン・ジョンウンも訳している斎藤真理子さんのご尽力のおかげもあるのだろう。斎藤さんは『カステラ』も訳されており、日本における韓国文学の発展に一役も二役も、多分五百役くらい買っている。海外文学を読んでいていつも思うのは、翻訳者の方々の努力があってこその享楽だなということ。本当にいつもありがとうございます。
では本題。『野蛮なアリスさん』はこんなふうに始まる。
私の名前はアリシア。女装ホームレスとして、四つ角に立っている。(p.7)
タバコに火をつけるとき、小銭を探してポケットをひっくり返すとき、息を吸い込むとき、落ちている手袋を拾うとき、傘をひらくとき、冗談を言って笑うとき、ラテを飲むとき、宝くじの番号を照合するとき、バス停で何気なく振り向くとき、アリシアの体臭をかぐはずだ。君は顔をしかめる。不快な気分になる。アリシアはそんなふうに不快がる君がかわいい。アリシアが君の無防備な粘膜に貼り付くよ。オナモミみたいな鉤になった小さな棘で、君にしっかり、とりつく。アリシアはそれをやるために存在している。他の理由はない。みにくく、きたなく、気持ち悪く、追い払おうとするとなおさら喜び、嬉々として、奇々として、鬼気として、くっつく。(p.8)
君はコモリを憶えているか。(p.8)
まずこのお話の話者は誰なのか、が最初からわからない。一人称のアリシアが語り、二人称で呼びかけられ、その後三人称でアリシアの生活が描かれていく。そして時折、一人称が顔を出す。この人称混在に対する私なりの解釈はひとまず後回しにするとして、このお話の舞台、「コモリ」という土地とその背景から見ていこう。
解説によるとコモリには明確なモデルがあって、ソウル市のはずれにある空港洞と麻谷洞という地域だそうだ。この地域は韓国の都市開発事業に乗り切ることができず、「ソウル最後といわれる広い空き地と農地が残された(p.193 訳者あとがき)」土地。マンションや高層ビルが次々と建設されていき、不動産投機によって富めるものはさらに富み、貧しいものは取り残され、昨日までの隣人は撤去を強要する敵となり、不動産をめぐる欲望と暴力という韓国の都市再開発事業の澱がこの作品の背景にある。
(韓国の都市再開発事業については、本書の訳者あとがきに詳しく、またファン・ジョンウン本人のあとがきにもあるので参照されたし)
そんなコモリという土地で主人公の少年、アリシアは暮らしている。コモリは「都市開発から取り残された土地」であり、「中途半端な建設事業」の割を食ってしまった土地。常に汚水が流れ、空気は臭く澱み、住民は鬱屈を抱え、暴力・暴言でそれを発散し、暮らしている。要するにスラムだ。
余談だが、中国・韓国・台湾あたりの小説を読んでいると汚泥した土地に暮らす人々の描写に出くわすことが多々あるけれど(これは私の選書傾向のせいもあるが)往々にして汚水でびちゃびちゃしている。気候のせいもあるのだろうが、乾いて痩せた土地で・・・というよりは大体皆さん足元がびちゃびちゃしていてじっとり汗をかき垢と糞と尿にまみれている。しかしこのイメージはおそらく残雪の『黄泥街』(長らく絶版だったがこのたび白水Uブックスより復刊とあいなりました!!ヤッター!!)による強烈なインパクトのせいも多分にあるだろうな。
コモリも同様に、下水処理場があり、汚水のにおいが常に漂っている。食用のための犬を劣悪な環境で飼い、繁殖させ、彼らは勿論糞尿にまみれ、アリシアたちが食事をする場所はいつも油やよくわからないものでベタベタしている。弟は学校で便を漏らす。親友の父はゴミやガラクタを売って暮らしている。
そんな環境下で更に追い打ちをかけるように、アリシアの母は日常的にアリシアと弟を殴る。それはもう、獣のように。罵倒語を叫びながら殴る殴る。本書で繰り返されるのが「クサレオメコ」という語。
原文では、女性性器をさす名詞と「やる」という同士が組み合わさった「シバル」という、最強の罵倒語である。(...)性的な単語を含むが、女性を貶めるというよりは、人と状況に対する呪詛の混じった罵倒語とでもいおうか。
p.197 訳者あとがき
アリシアの母はただクサレオメコと言うだけではない。あのアマはクサレオメコだと彼女が言うとき、そのアマはほんもののクサレオメコになる。百パーセント濃縮の、百万年の怨恨をこめた、百万年も千万年もそのまま腐っていきそうなクサレオメコになる。(p.28)
何かがひどく気にさわったのか、彼をまた庭に引きずり出して体を押したり引いたりして怒りだした。彼女にはそういうときがあり、そうなると止まらない。そんなとき彼女は人というより、状態といった方がいいものになり、焼きを入れた鋼鉄みたいに熱く、強くなり、まわりの温度まで変えてしまう。クサレオメコになるのだ。持続し、加速していく途中で脈絡は蒸発し、ただもうクサレオメコ化したというしかない状態になる。
> あれを言うとき彼女は、言いたくて言っているのだから。そんなとき彼女は一滴の雨だれみたいに透明で、単純だ。殴りたくて殴っているのだ。(p.45)
とても残念なことだけれど、私はアリシアの母の、この衝動がとても良くわかる。私は物理的な暴力こそ振るわないが、怒りが怒りを再生産し続けて永久機関のようになってしまう、つまりクサレオメコ状態を何度も何度も経験した。他者にそれを言葉でぶつけたこともある。今でこそ歳をとりだいぶ落ち着いたが、今後も無いとは言い切れない。自分で止められないのだ。何らかの疾患かもしれないが、クサレオメコ状態になってしまうと、病名があったところで薬を飲んだところでそんなことは何の助けにもならないのだ。
アリシアは一度だけ銀河を見たことがある。(...)星も何もない銀河空間は、あれからどれくら広がっただろう。とにかく、すごいんだろう。巨大で美しいはずだ。(...)膨張して膨張して、星と星の間隔が途方もなく広がってしまった銀河の中で、アリシアは点の一個にもならないはずだ。ほこりの一個にも及ばないアリシアの苦痛なんて、何ものでもないはずだ。
そんな銀河はクソだ。
アリシアが受けている「苦痛」も同じなのだろう。何かと比較して「これくらいなんでもない」なんて、何の助けにもならない。なぜなら当人にとってはそれが全てだから。怒りも苦痛も純粋な「状態」と化したとき、人は輪郭があやふやになる。外も内もなくなる。というか、内しかなくなる。私が執拗に本を読み続ける理由のひとつはここにあるのだとも思う。怒り、悲しみ、恨み、その他のマイナスな「状態」になってしまわないように。自分の輪郭を見失わないように。外があることを認識し続けるために。自身の内だけで完結してしまわないように (それはとても危険だから) 。
本書は「内」「外」「再び、外」という3章に分かれて構成されている。
「内」で描かれているのは上述した、アリシアとその周辺人物(弟、親友、父母、腹違いの兄姉など)の「外が見えなくなった状態の内側」なのだろう。母は殴り続け、アリシア兄弟は苦しみ憎み続け、父はそれらを完全に無視し続け、親友はゴミを抱え続ける。彼らはそこから出られない。アリシアは、離れて暮らしている腹違いの兄姉に現状を訴えようともするが、何も言えずに終わってしまう。
「外」ではアリシアは現状を打破しようと役所に赴いて相談したり(予想通り徒労に終わるのだが)、新しい住民と関わり合ったりして外界と接触しはじめる。コモリにも次々とマンションが建ち、人が増えてくる。
何なんだこの町。・・・・・・なんでこんなになんにもねーの?変な町だな。(p.103)
「なんにもねー」町で子どもたちが暴力や貧困にさらされながら、そこから出ることが出来ないまま、周りの大人達は暴力を再生産する。アリシアたちを生んだせいで子宮がだめになった、それがなければもっといいところに行けたのにと語る母、父に夢をぶち壊されたと語る兄、補償問題と欲に突き動かされながら罵倒し合い、肉を喰らい続ける隣人たち。クサレオメコ状態になるための理由はそこかしこに転がっていて、いつだって準備万端。
つかの間の現実逃避としてアリシアが弟に語るおとぎ話ですら、安穏なものではない。繰り返される子殺しの悪夢、道端で腐って膨れ上がる犬のビジョン。それらが執拗に繰り返される。悪夢は、終わらない。
まだ落ちてて、今も落ちてるんだ。すごく暗くて長い穴の中を落ちながら、アリス少年が思うんだ、ぼくずいぶん前に兎一匹追っかけて穴に落ちたんだけど・・・・・・どんなに落ちても底に着かないな・・・・・・ぼく、ただ落ちている・・・・・・落ちて、落ちて、落ちて・・・・・・ずっとずっと・・・・・・もう兎も見えないのにずっと・・・・・・って考えながら落ちていくんだ。(p.150)
そして私達に問いかけられる。「君は、どこまで来ているかな」と。
このお話の話者はアリシア。一人称で「私の名前はアリシア」と名乗り、読者である私達に対して「君はコモリを憶えているか」と問う。自身を客体化して三人称の物語、終わらない悪夢としてアリシアの物語を語る。時折、読者の並走を確認するように「君は、どこまで来ているかな」と問う。それが人称混在の所以なのだろうが、私はそれだけではない気がする。
アリシアは、私であり、あなたでもあるのだ。
アリシアだけではない。アリシアの弟も、母も、父も、欲望にまみれた利己的な隣人たちも。だからアリシアは問う。
「君は、どこまで来ているかな」と。
暴力も苦痛もすぐそばにある。隣どころか、私の中にある。私の粘膜に貼り付き、いつまでも消えない臭いを残す。私は鼻をかむが、臭いは消え去らない。
君の無防備な粘膜にアリシアが貼り付く。(…)君が食べ、眠るこの街に、今アリシアもいる。君はそれを自然なことと言うだろうか。アリシアを、一時的な存在にすぎないと言うだろうか。アリシアの匂い、アリシアの服装、アリシアの軌跡のすべてを、いつか過ぎ去っていくものだと言うだろうか。やがて消えるものだと、アリシアも、ついには他のすべてのものと同じように消えていくと、言うだろうか。(p.183)
他人事だ、フィクションだ、自分とは関係ない、嘘だ、まやかしだ、偽善者だ、おとぎ話だ、そうやって他者の物語を貶める言葉は毎日いたるところで耳にする。でも果たしてそうなのか。それは自身の内しか見えていないからではないのか?
外を意識したとき、そして外と自身の境界が曖昧になる感触と、外があるから自身の輪郭を保てることに気づいたとき、他者の物語は私の物語になる。少なくとも私はそうだ。
コモリという穴に落ち続け、地面にも到達できなかった弟。彼が礎石に刻んだ自身の名前は、もうない。
その名前は、雨水とほこりにまみれて消し去られ、もうそこにない。(p.178)
その名前が、あなたや私の名前ではないと、言えるだろうか?
女装ホームレスというアリシアのモデルは、実際に大阪を歩いていたホームレスだと作者は言う。
「再び、外」へ。私は新宿の雑踏で、似たような姿をした何人ものアリシアを見かけたことがあるし、これからも見かけるだろう。彼らの姿を目にするとき、彼らの臭いが風にのって漂ってくるとき、顔をしかめるかもしれないが、彼らは、私の粘膜にとりついたアリシアだ。私と彼らを隔てるものは確実にあるが、私と彼らは地続きだ。私と彼らをつなぐものが、本書のような作品なのだと思う。
君と私の物語はいつか終わる。しかし終わりはゆっくりと訪れ、君と私は苦痛を味わうだろう。(p.185)