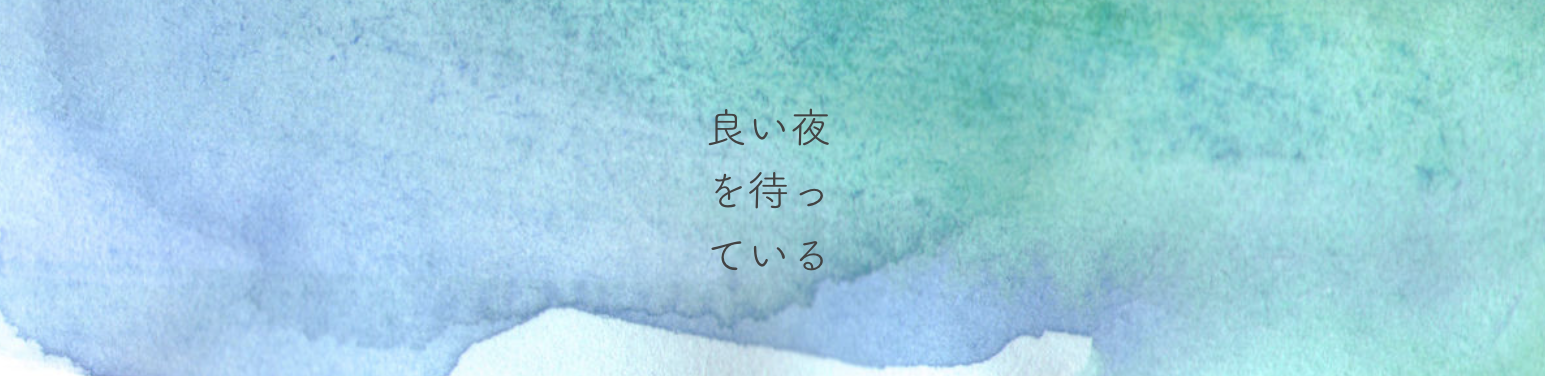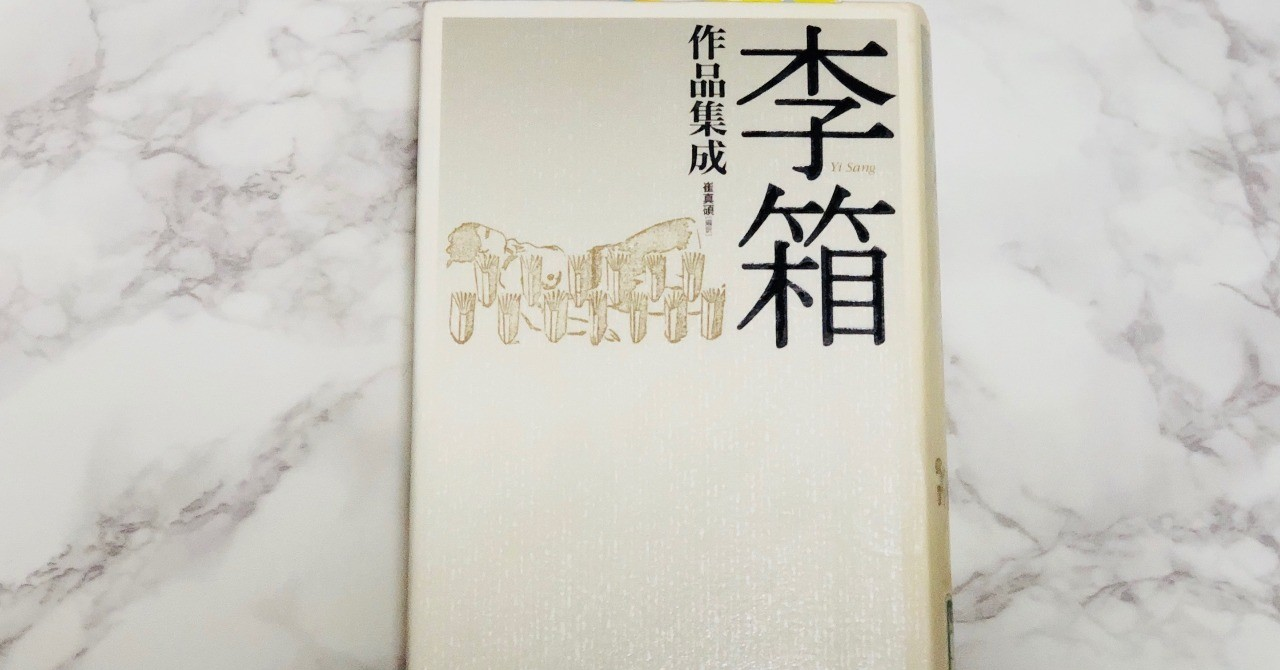
3カ国目は北朝鮮に行こうとしていたのだが、北朝鮮、現代の作品がからきし見つからない。いやもっと本気で探せばあるのかも知れないが、私の検索力と気力(もとから残機が3くらいしかない)では南北分断後で北の作品、となると政治情勢もあるから仕方ないのだろうが、脱北ルポタージュくらいしか見当たらず。ということで、今回は「朝鮮」という大きな括りで南北分断前、まだ日本統治下にあった時代の朝鮮の作家、李箱を読んでみた。
李箱(イサン)は1910年京城府(今のソウル)生まれ。享年26歳という若さで亡くなった朝鮮を代表するモダニズム作家。韓国では李箱の名が冠された「李箱文学賞」というものもあって、日本でもおなじみのパク・ミンギュ(『カステラ』『ピンポン』などの作者)も受賞している。小説、随筆、詩のみならず同人仲間の朴泰遠(パク・テウォン)の作品に挿絵を描いたりもしていて実に多才。
李箱は「異常」「理想」(イサン)と同じ音で、その名の通り作品も前衛的で難解、夭折した天才作家と称されている。確かに詩に関しては、「THE・モダニズム詩やで!オラオラ!」という印象の難解さがある(笑)。ちなみに彼が新聞に詩を連載していた頃(1930年代)は読者から精神異常者の文章だとしてクレームが来たそうだ。しかし、小説や随筆に関してはさほど小難しいわけでもなく楽しめるので、深く考えず手にとってみて欲しい。ただ残念なことに絶版なので、図書館や古書店などでぜひ。
全体の雑な印象としては、誤解を恐れず言うならば「インテリ引きこもり文学」である。小説の主人公はほとんど寝てばかり、たまにカフェでダラダラしたり街を徘徊したり、怠け放題のひきこもりである。妻の稼ぎで暮らしており、妻は何度も家出を繰り返す。まあ要するにヒモだ。
すべてが面倒だった。足を引きずる妻をむりやりに送りだしておいてから彼は人間世界のあくびを一度大きくした。際限なく怠けるのがやっぱりいちばんだ。
「蜘蛛、豚に会う」p.28
しかし不思議とムカついたりせず読めるのは、洗練された文体と、薄暗い部屋で眠り続ける彼(ら)が抱く厭世観が、全体を重苦しく覆うのではなく、断片的に挿入されることで作品にどこか軽やかさをもたらしているからだろう。
今回の李箱に合わせて同時代の朝鮮作家の作品を短編でいくつか読んだのだが、その作品の多くが労働者階級・農民たちの苦悩や困窮した日々をえがくプロレタリア文学といった類のもので、背中にのしかかるような重たさを感じた。しかし李箱と前述した朴泰遠の作品は、それらと比較するとかなり異色。もちろん豊かではない人々の話であることには変わりはないのだが、どこかあっけらかんとしている。
また、李箱の恋愛や女性のえがき方も、この時代のものとしてはなかなか斬新で面白い。もちろん、1930年代を生きた彼には男尊女卑的な思想が根底にあるが、登場する女性の姿はしたたかで強い。
「おまえが自分の言うように、二人の男、あるいは実際のところそれよりもずっと多くの男に捧げた肉体を抱え込んで、そんなにも豪気にまた正々堂々と俺の城門に闖入できるのが鉄面皮でなくて何と言うのか?」
「あなたは無数の売春婦に、あなたのおっしゃるその高貴な肉体を廉価で見物させられました。同じことですよ」「はは!おまえはこういう社会の仕組みをうっかりと忘れてしまったのだな。おまえはここをチベットだと思っているのか。そうでなければ男も哺乳行為をしていたピテカントロプス時代だと思っているのか。可笑しいなぁ。申し訳ないが男には肉体という観念がない。理解できるかい?」
「申し訳ないですが、あなたこそこういう社会の仕組みをどうにも急速度で逆行されてるようです。貞操というものは一対一の確立にあります。掠奪結婚が今もあるとお思いになるのですか?」
「肉体に対する男の権限における嫉妬は何か襤褸切れのような教養の切れ端ではない。本能である。おまえはこの本能を無視したり、その稚気満々な教養の手袋で整理したりする能力が通用すると思っているのか?」
「そうしたら私も平等で温順にあなたが定義される『本能』によってあなたの過去を嫉妬することにいたします。さあーー私たち、数字ではっきりさせましょうか?」
「童骸」p.94
急速な近代化を進めていた朝鮮を、奔放な恋愛観を持つ女性になぞらえ、それに対比するように旧時代の思想に囚われ続ける李箱。ギャップを彼は「びっこ」という言葉で表現している。ちぐはぐで噛み合わない男女の姿はこの集成を通してあちこちに表れる。19世紀と20世紀の混在と葛藤が彼の作品の主要なモチーフである、という点は訳者解説(解説というには豪華すぎるくらい充実していて、本文と合わせて一読の価値は大いにある)に詳しいのでここで深くは触れないが、早足でつかつかと歩みを進める女性に対して、べそをかきながら引きこもったりする男性(李箱)の姿はどこか可笑しく、哀しい。
特にお気に入りは、先に引用した「蜘蛛、豚に会う」と「翼」というふたつの小説。
「蜘蛛、豚に会う」は女給を勤める妻が職場で「白豚」(取引先専務)に蹴られて階段から落ち「白豚」から慰謝料をもらうまでの話。夫の一人称視点で、妻に寄生しダラダラと眠って過ごすだけの夫自身と、やせ細っていく妻に「蜘蛛」を幻視しながら、彼の意識があちこちに飛び火していく様子が断続的にえがかれているのがとてもおもしろい。
「翼」はこの集成の中でも白眉の傑作。李箱の作品の中でも最も有名な作品と思われるし、とても短いのでこの作品だけでもぜひ読んでみて欲しい!
「翼」は私娼宿に住む妻と、こちらもまた一日のほとんどを寝て過ごす夫の話。彼らの住まいは同じ構造の部屋が18所帯も並ぶ「三十三番地」。昼間は静まり返り、夜になると様々な音や匂いがして賑わい出す。居住者は若い女ばかり、という閉じられた世界。それはどこか幻想的な趣すらある。
主人公の「僕」はすこし知能が低く、お金の使い方も、妻の職業もよくわかっていない子供のような人物。たまに妻の部屋に忍び込んでは化粧品の瓶のにおいを嗅ぎ、それらが光に透けるさまを眺めて楽しむ。食料も妻が部屋に運び入れるものを口にするだけ。たまに妻の客が部屋に来ると逃げるようにして街へ出たり、部屋でじっと物音を立てず蒲団で縮こまっている。あまりに彼の生活が人間界と乖離しているため、この夫が本当に「人間の夫」なのかもわからなくなり、私は読んだ当初、妻の飼い犬なのかとも思っていたくらい。
僕は自分が地球上に住み、僕のこうして生きている地球が疾風迅雷の速力で広大無辺の空間を駆け抜けているということを考えたとき、すごく虚しい気持ちになった。僕はこんなに忙しい地球の上では眩暈がしそうで一刻もはやくここから降りてしまいたかった。
「翼」p.43
引きこもりも厭世感もここに極まれりである。ここまでくるとよほど清々しい。日がな一日蒲団の上で「研究」と称し思索を重ねる彼の姿は痛々しくも純粋な哲学者のよう。
この作品も近代性(日本人街)と植民地性(朝鮮人街)の二重空間を映したものであるということが解説には書かれておりなるほど、という感はあるが、その背景をまったく考慮せずとも、この頽廃とした空気感と、一種の幻想文学のような雰囲気は味わえるし、私はこの作品を脳内の本棚(ジャンル別)で山尾悠子と近い棚に配架している。
他にも、ド田舎の生活に辟易とし、そこで暮らすのんきな人々を小馬鹿にしながらも彼らの生活からほとばしる純粋な生命力にあてられて、一瞬「まあずいぶん寝たし起き上がってやるか」となるが「でもやっぱお外こわい」となる、プロ引きこもりとしての魂が光るタイトルどおりの「倦怠」という随筆もまた素晴らしい。
部屋に戻ってきて私は自らを省みる。すべてのことから絶縁された今の私の生活ーー自殺の端緒さえ探す術のない今の私の生活はいかにも倦怠の極倦怠そのものである。
「倦怠」p.259
「倦怠」は本書の付録で小森陽一がジャック・デリダを軸に解題しているのでそちらも合わせて読むとさらに楽しめる。
しかし李箱、私の力不足もあるが、あらすじを書くと全く面白くなさそうで笑ってしまうな。紹介されているあらすじがつまらないために埋もれている傑作は山程あるが、もしかしたら李箱も(日本では)そのひとつなのかもしれない。
北朝鮮の作品を探していて、やはり今でも北緯38度線で分断され続け、その文化や芸術が、韓国に比べてなかなか開放されていない状況をあらためて認識し心苦しくなった。北朝鮮の人々がプロパガンダ以外で日々どのような芸術に触れているのかもあまり分からないが、少しでもそこに住む人々が、心穏やかな日常を送れることを、そして豊かな芸術に触れられることを祈る。そして、北朝鮮から生まれている(であろう)優れた芸術が、世界に広がっていくことを祈る。
李箱 崔真碩訳『李箱作品集成』作品社 2006年9月初版
(絶版のため、版元のリンクなし)
参考文献:大村益夫・布袋敏博編
『朝鮮近代文学選集3 短編小説集 朴泰遠「小説家仇甫氏の一日」ほか十三編』
平凡社 2006年9月初版

短編小説集 朴泰遠「小説家仇甫氏の一日」ほか (朝鮮近代文学選集)
- 作者: 朴泰遠
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 2006/09/26
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る