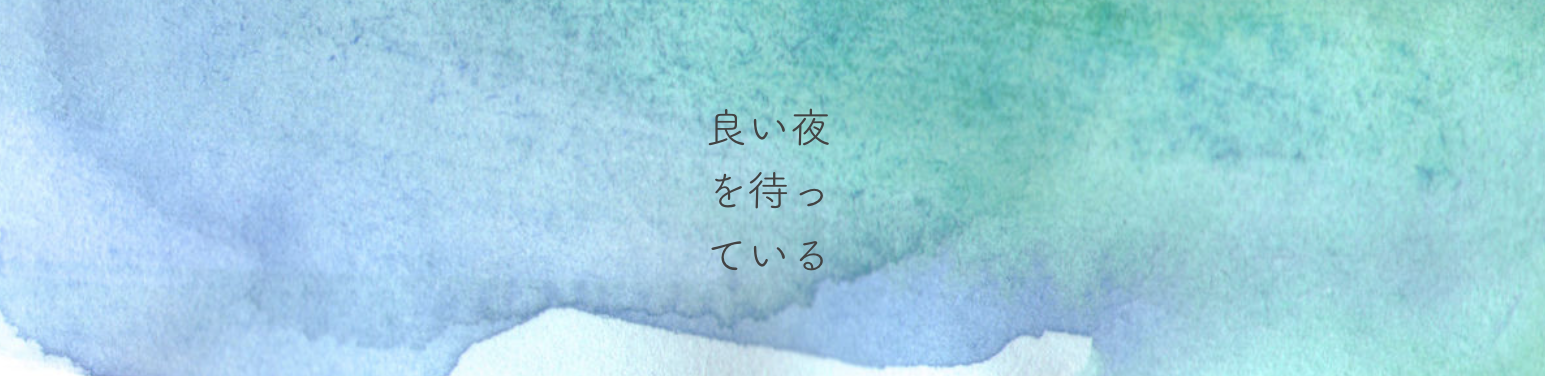アステリオンの旅行鞄、栄えある第1カ国目。まずは日本から。
今回選んだのは吉田知子の短編選集。完全にタイトル勝ちの『脳天壊了(のうてんふぁいら)』。意味としては「大馬鹿者」とか、「頭イカれちゃってる」「イっちゃってる」というようなところ。Wikiによると、日中戦争時に日本陸軍が使っていた中国口語と日本語が微妙に混ざった言葉のひとつとのこと。今で言うIT系カタカナ語的なものかもしれない。
脳天壊了。あまり良い意味ではないし歴史的背景からすると笑えないけれど、語感がキャッチーすぎて口の中で何度も唱えてしまう。
のうてん、ふぁいら。のうてん、ふぁいら。
表題作は一発目に収録されている。これが傑作で、端的に言うと「こじらせまくった不気味系BL(百合)」。(百合)の意味は最後に説明するが、とにかく、この選集、全体を通して不条理・不気味な短編が粒ぞろい。その中でも群を抜いて素晴らしかったのはやっぱり表題作。
何度か読み返したのだが、読めば読むほど胸が苦しくなる。
主人公・杢平とその連れ、中瀬(本文にも「連れ」とあるし「夫婦以上」ともあるので公式)は幼馴染で、満州で再会し親密になる。戦争が終わってふたりとも満州から引き揚げ、いま中瀬は肺癌で死にかけていて寝たきりになっている。そんな彼を足繁く見舞う杢平。見舞ったところで中瀬は白目をむいて寝ているだけで一言も発しない。ただ静かに彼を看取るためなのか、彼の死への幾ばくかの抵抗なのかは分からないが、中瀬宅に通い続ける杢平。
中瀬の所へ行くときだけ決断がつかない。散歩のつもりにして家を出る。ただの散歩という習慣は杢平にはないので、結局、散歩すなわち中瀬と決っているのに、自分ではそれを認めたくなくて、一時間も歩いてから「ついでだから」と自分自身に弁解する。(p.22)
ね、もうしょっぱなからしんどい。切なすぎてしんどい。
杢平に去来する迷妄・幻覚と、杢平の中瀬に対する憎悪、嫉妬、愛情、「中瀬が死ぬ」ことの恐怖と、いっそはやく死んでしまえという気持ち、その他諸々の感情群。これらが本当に美しいグラデーションで描かれている(ここで言う「美しい」はキラキラして色が綺麗とかではなく、場面の移り変わりがシームレス、というような意味)。
中瀬は運のいい男に違いない。(…)いつ、どうやって中瀬は帰国したのか。杢平はついに中瀬にきけなかった。(…)中瀬は運がいい。中瀬だけ運がいい。
杢平は道沿いの波形鉄板の塀を拳でなぐった。間の抜けた大きな音がした。薄い鉄板は下のほうから錆びてきている。赤錆の色が伸びあがって上へ拡がっているのが、一瞬、炎の色に見えた。炎だけではない。その間に樹の皮のように盛りあがり、崩れ落ちようとしているものがある。傷ついて動けないでいる。うずくまっている。頭のない鳥がいる。縛られた人間。穴になった眼窩から黒い水が流れでて炎と一つになっている。もがきながら這っている女。胸に腐った肉を抱きしめている。肉は銀灰色に光っている。無数の蠅だった。胸の子供は融け落ちようとしている。(p.25)
もうここは胸がはちゃめちゃに苦しくなる。杢平の脳裏に去来する幾多の中瀬とのエピソードと、避けられぬ死へのやるせなさ、悔しさ、それらが相まって視せる幻覚。全体として中瀬への愛が明示されている箇所はほぼ無いのだけれど、これが愛でなくてなんなのか。
杢平が幻視する光景の描写は若干の残雪みがあって、それが私が脳天壊了にドはまりした理由のひとつでもある。光景としては決して綺麗なものではなくて、暗くて不気味で臭そうで、それなのになぜか純粋さがきらめく感じ。
しまいには杢平の中でも巨大感情が処理しきれなくなったのか犬を殴り殺しては「脳天壊了」を文字通り実践してしまい、
「犬の頭をな、こうやって打ち砕いてやったらな、脳のミソがパァッと散ってよう」(p.33)
さらには中瀬なら死体になったとて価値がある、死体を見世物にして金を稼げばいい、なんと穴も空いている(中瀬は怪我で足に穴が空いたままになっている)などと言い出す。
「(…)お前なら大丈夫だ。一等品の死体になれるて。死体っちゅう意味しかない死体さ。わかるか。他の意味がついちゃ純粋じゃなくなるってこんさ。お前はぴったりだよな。まるまる死体だ。他のことは誰も何も考えんわけだ。はじめっから死体だったみたいな死体。まっさらな死体。ああ、これが死体だという見本みたいな死体。なぁ、おあつらえむきだろう、お前なら。これ以上はないて」(p.37)
これは、死んでも一緒にいたいですっていう一種のプロポーズではなかろうか。
「死は誰にでも訪れるのだから仕方ない」「でもなんだってお前が死ななきゃいけないんだよ」「いっそ早く死ね」「むしろ俺を殺せ」
こう書いてしまうと死に別れモノのお約束テンプレセリフだけれど、それを本人たちには決して語らせず、事物と記憶と幻覚のグラデーションと、なにか本質を避けたような、照れ隠しのような会話で浮かび上がらせる筆致は本当にすごい。
そのすごさの顕著な例が「松」の描写。中瀬のメタファーとして描かれている「松」が、冒頭、中盤、ラストに登場するのだが、全体を読み通してからもう一度この「松」の部分だけ読み返してみると、こっちが脳天壊了しそうになる。
杢平は川竹には目もくれない。松を見る。空地には何本か松がはえているが、杢平が見ているのは、その中の一本だけだ。杢平の狭い視野に全体がうつるのは、その松しかない。(...)見ているうちに、杢平はそれが木だという気がしなくなる。中瀬が立っている。中瀬が杢平を見おろしている。杢平に襲いかかろうとする。(p.7)
中瀬しか見てない、見えてない、ぞっこん中瀬一途ラブだと。でもそれだけではない「巨大感情」が渦巻いているので、
まだ風は吹いている。もっと吹け、と杢平は心の中で念じる。隣りの空地に勝手にはえたあの松が折れるまで吹け。が、松が折れたところで何ほどの事件でもあるまい。あそこに松がはえているのに何人が気がついているか。あれが折れて腐ってなくなっても誰も知らないでいる。ただの松なのだ。庭木にもならぬ、雑草と同じ価値しかないつまらぬ松。すうっと力が抜ける。ただの松。(p.15)
こんなことを言ってしまう。勝手に俺の心に入ってきやがって、たいした輩でもないくせに。そこいらの人間と同じ、特別誰にも気づかれないし(でも俺は気づいているしお前を見出しているが)死んだってどってことない。全然平気(と自分に言い聞かせている)。強がりかわいいかよ。
闇の向うに、ぼうっと松の姿が見える。まだ立っている。杢平を見ている。(p.41)
ここはクライマックスの部分。いよいよ中瀬が死ぬとき、その死を素直に認められない杢平が幻視する松(=中瀬)。
ここまでの感情の揺れ動きを心理描写をほぼせずにたった42頁で描ききるのは天才の所業でなくて何というのか。
最初に「こじらせまくった不気味系BL(百合)」と言ったけれど、この感情の揺れ動き、百合だと思うのだ。おっさん二人の話だが、この感情は百合。概念としての百合。思念体としての百合。何言ってるか自分でもわからない。でもこの感情は、最近話題になっていた宮澤伊織氏のインタビューを読んでいただければ少しはわかっていただけるかもしれない。
・・・わかっていただけないかもしれない。でもとにかく、この感情の奔流を肌で感じてほしいです。表題作だけだったら立ち読みでも読み終われるくらい短いお話なので、ぜひ。
他にも、人間の醜悪さと他の動物との境界が曖昧になる恐ろしさが描かれた「ニュージーランド」、ひねくれ貧乏喪女(これ死語?)のたのしくないまいにち・ごはんはまいにちゆかりごはん!「乞食谷」、タイトルDEネタバレ賞「お供え」などなど、本当に全部面白い選集。巻末には町田康が書いた〈自分が高校で国語を教えていたら、「脳天壊了」でどんな試験問題をだすか〉という体の四題が掲載されている。
吉田知子、本当に良かった。他のも読んでみたい。
蛇足。これはちょっと長くなるから別エントリにしようと思うのだが、日本の不気味・不条理系の小説って、私が読んだ範囲内の話にはなるが、やはり独特の湿度がある。生暖かったり、冷たかったり、温度は様々だけれどどれもしっとりしている気がする。それが気候のせいなのか、日本語のもたらす音やひらがな・漢字のイメージから想起されるものなのか、源泉がどこなのかわからないけれど。吉田知子の小説にもそれを感じた。
第一カ国目からこんな傑作に出会ってしまって幸先良すぎて逆に心配。
次回はお隣り、韓国に行ってきます。
ではまた。