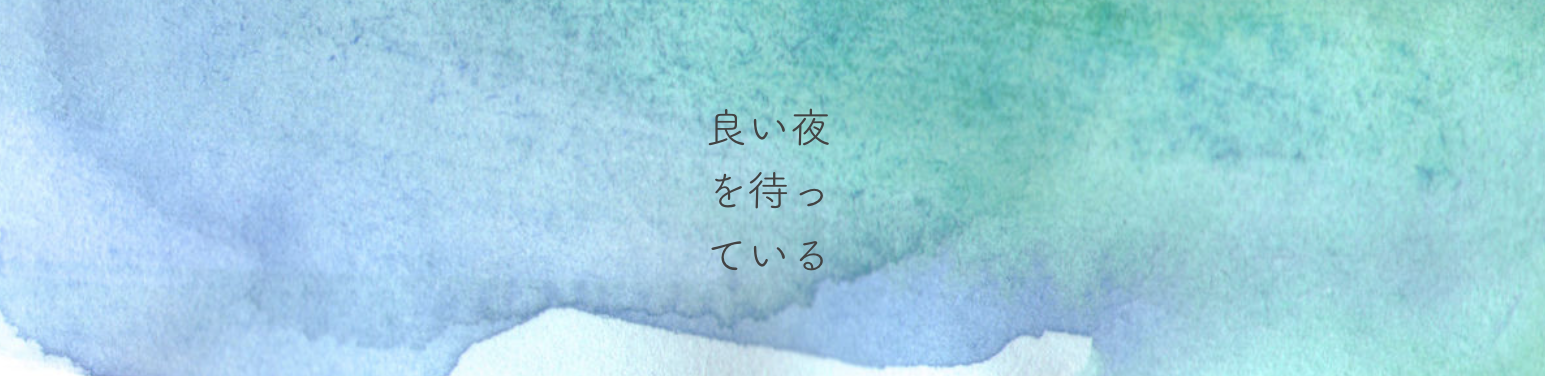私は今、何を読み終わったのか。
これほどまでに良い意味で「何を読んだのか」が読後に分からなくなる小説も珍しいと思う。それくらい『零號琴』は怒涛のうねりとその中に含まれる幾多の小ネタが緻密に設計され盛り付けられた特上の一品。それらの味わいが豊穣な上に盛り付けも美麗、だからこそお腹がいっぱいなことだけは確かな事実としてあるけれど、自分が今何を食べたのかが分からなくなる。そんな作品。
舞台ははるか未来。特殊楽器技芸士と呼ばれる、空間も重力も歪めてしまうような特殊な「楽器」を操り調教する職人セルジゥ・トロムボノクとその相棒、見た目は美少年で性欲旺盛、しかしながら誰よりも年上で怒らせると(文字通り)破壊神となるシェリュバンがひょんなことから大富豪パウル・フェアフーフェンと出会い、トロムボノクはある依頼をもちかけられる。それは「美縟」という惑星で行われる、開府500年を記念した祭りで伝説の楽器「美玉鐘」を用いて秘曲 <零號琴> を演奏する、というものだった・・・。
というのが物語の始まり。
美縟では假劇と呼ばれる音楽劇の文化があり、そこでは人びとはもれなく「假面」を装着して観劇するのだが、これは装着することで、その「假面」に割り当てられた役をまさしく心身ともに体験することができる(VRゴーグルの進化形みたいなもの?精神侵食型VRゴーグルとでも言うべきか)。
「(…)美縟民族の長大な物語――<美縟のサーガ>には、数え切れないほど多くの神々、英雄、知者、怪物が登場する。そして詩人も。かれの背負った運命と痛切な感情のことごとくを強烈な心的情景に造形して、假面に埋め込んである」
(…)
「この中に――假面の奥に、いつもあの光景があるのです。多くの人を焚殺しつづける焔、重油を湛えたような闇、そして鳥の啼き声が。
サーガの神々、英雄、怪物はそれぞれに物語を持っている。假面を着けることは、その物語を我とわが身で引き受けるという積極的な意志を意味します。(…)」
p.32-33
観客も假面を着けることで一人ひとりが劇に参加し、自身の「假面」に割り当てられた劇中の役割を演じていく、というのが「假劇」の仕組み。その大假劇がこの物語の主題となっていくのだが、この劇に盛り込まれている小ネタがものすごい量。
私の分かる範囲だけでもプリキュア、ナウシカ、まどマギ、ゴレンジャー、エヴァ、その他SF小説のあれやこれや。そもそもこの記念すべき式典で演じられる假劇自体が「あしたもフリギア!」という大人気番組の再解釈を盛り込んだ脚本、という設定。
それらの小ネタ(元ネタ)をひとつひとつ洗い出して解釈するのもひとつの楽しみ方とは思うが、私はそれをやってしまうと作者の術中(?)にハマる気がしてあまりそこに注視したくないというのが正直なところ。
<ここから先はネタバレが含まれるので未読の方は注意>
たしかにそれらの元ネタを「假劇」という舞台装置で踊らせる手腕は本当に凄い。プリキュア未履修の私でもここに盛り込まれたストーリーだけでちょっと泣きそうになったし、地下からドロドロの巨神兵もどきが引きずり出されるところなんかニヤニヤが止まらないし、シェリュバンが着用する羽目になる可愛い衣装、クライマックスの「まじょの大時計」と主人公が「くさび」となってその悪循環を止めるというモチーフはまどマギ最終回のそれだし、「仮面」といえばあのおそろしい子、マヤだって出てくる。それらだけでも十分すぎるほどにエンタメ性がある。
また、この一大假劇の様子が飛浩隆節で描かれているので一筋縄ではいかない緻密な美しさがある。その光景は圧倒的スケールのなのに大雑把と感じるところはほとんどなくて、ひとつひとつのことばの網目が整然と並んで輝きを放っている。まさにひとつひとつの楽器が奏でる音粒が重なり合って響きあうオーケストラの交響曲のような。
帯で書かれている「想像しえぬものが、想像された」というのは物語後半で明かされる美縟の過去とリンクする一文だが、それはこの作品全体の印象とも重なる。帯に倣って言うならば「言語化しえぬものが、言語化された」とでも言おうか。
それが一番顕著なのが、p. 230-232の特殊楽器奏者であるヌウラ・ヌウラが美玉鐘を演奏するシーン。ここは本当に鳥肌が立つほどの描写。鳥肌どころかヌウラ・ヌウラと同じく「髪という髪がさあっと逆立っ」(p.230)ってしまう。
でも私がこの作品で一番気になったのは「時間」と「創作」についての解釈と、そこから導き出される「物語論」としての『零號琴』。ここから先は超解釈で、おそらく綻びが多分にあるので、あくまでノート的なものとしてご笑覧いただければ幸い。
登場人物のひとり、書画工芸を生業とする鳴田堂が、先述したヌウラ・ヌウラの美玉鐘試奏を聴いたときの思索をまずは引用しよう。
音楽が「時間を追って変化を作り出して行く(形を作り出して行く)芸術」であるとすれば、彫刻は「空間の中に形を作り出して行く(変化を作り出して行く)芸術」だといえる。
p219
塑像というのは時間に対して対称で、時間が経過すればその分のカタチが出来上がる。一方、音楽は時間に対して非対称で、時間が経過するとともに変化して行く。
では、この『零號琴』という作品、つまり「物語」はどうか。物語を読むという意味では時間に対しての変化はほぼ音楽と同じだろう。読み進めるにつれてことばは過ぎ去ってゆく。記述するという意味では塑像と同じ。時間とともに形作られて行く。
読み進めるつれてことばは過ぎ去って行くが、書くことでそれは形作られてゆく。つまり、物語を読む/創造するという行為は、時間に対しての変化をそれぞれ担っているのではないか。
内部で無数の音が生まれては消えているが、全体としては何の変化も作り出さない――時間方向に対称な音響だ。
音響彫刻。「音を発する彫刻」ではなく「ただ音のみで成り立つ彫刻」。
(…)
しかし音のみで成り立つ構造体があって、かりにその中から「時間」を排除できたら、あるいはかぎりなく小さくできたらそのとき音は聴こえなくなるのではないか。なぜなら、音楽とは、時間に対して非対称であることにその本質があるから。
p.220
この引用部分の「音」を「ことば」に置き換えたとき、物語はなくなってしまうのだろうか。しかし、「記憶」が「ことば」だけで構成されているものではないのなら、「物語」は持続し得る。そして繰り返し得る。物語は記憶の中に留まることが可能だから。
もしかして、『零號琴』と言う作品が目指した外郭は美玉鐘の音と同じ「音響彫刻」なのではないだろうか。そして、時間に対しての強い力(対称/非対称という本来相殺されてしまいそうな力を兼ね備えているなら強いに決まっている!)を持つ物語を「破壊」することが可能なのか、という問いも投げかけられているように思う。
美縟びとはかつて、自分自身を保つことを放棄した。物理的な身体を棄却して、永遠の物語の中に自分自身を閉じ込めることで生き延びようとした。
個別の人間、ひとりひとりのわたしを残すことをあきらめたのだ。
その代わり、物語になることにした。
人はかつて、世界の成り立ちと自らの感情生活を映し出す鏡として、神話を創り、英雄と怪物を生み出した。
この鏡はつねにひとの精神的営為が映し出されている。
そしてこの鏡からの反映を浴びることで、ひとは心を更新できる。ひとの精神はいともたやすく劣化しアウラを失うが、神話や物語にふれることで、ひとはみずからの精神を新しく産みなおすことができる。
p.486-487
音がもたらす徹底的な焼尽と新たな想像の創造。
世界の内面に構造化された音の爆心地。
グラウンド・ゼロ。
これが零號琴である。
そしてそれ以上のものでもある。
p.492
『零號琴』の物語は最終的に音楽を美縟から奪い去る。徹底的に焼き尽くす。終わらない物語(サーガ)を止めようとする。美縟びとたちの物語(生)に終止符を打とうとする。
「(…)つまり<零號琴>はかつてこの国でただ一度鳴り、死者の影を焼き付けた、音の閃光だ。
物理的な音はすぐに消えたかもしれない。
だが、いまも鳴り続けている。サーガとして、假面として、假劇として。
この呪いはまだ解除されていない」
(…)「あんたがふたりの子どもに投げた命題、『<零號琴>を破壊せよ』の真意は?」
(…)「いつまでも音を長引かせている鐘を止めようとしたらどうする?鐘に手を当てて響きを殺す。そうだろう」
p.552
しかし、物語は何度死んでも生まれ変わる。幾多の人の手によって、想像力によって。それは「二次創作」と呼ばれることもあるだろう。物語はある種、救いでもあり呪いでもあるのだ。
「『最終回』の向こうになにがあるか、生きて、見届けたい」
p.523
この欲望が、物語の再創造(想像)の原動力となる。
美縟から音楽が消えても、生き延びた人々はその焼け野原からまた懲りずに物語を編み出してしまうだろう。一旦焼けつくされたグラウンド・ゼロの「向こう側になにがあるか、生きて、見届けたい」と思うのだろう。そしてそれはいつか詩となり、メロディーを生み出し、音楽となるのかも知れない。焼け尽くされた物語は、アヴァンタイトルへと回帰する。
無辺の砂漠を想え。
(…)
少女は、長いあいだ彼女を封じていた「最終回」から解放され、あらたな「第一話」に飛び込んでいく。
アヴァンタイトル p.3-5
何度でも再生産される物語という切り口で『零號琴』を読んだとき、想起されたのはジーン・ウルフの『デス博士の島その他の物語』の一節だった。
「だけど、また本を最初から読みはじめれば、みんな帰ってくるんだよ。ゴロも、獣人も」
「ほんと?」
「ほんとうだとも」彼は立ちあがり、きみの髪をもみくしゃにする。「きみだってそうなんだ、タッキー。まだ小さいから理解できないかもしれないが、きみだって同じなんだよ」
『デス博士の島その他の物語』p.46
物語から出られないのは登場人物も、それを読み耽る私たちも同じなのかも知れない。でも、物語はもう一段階上に行くことも出来る。つまり、「この世界は外から見ることができるのだということ」(p597)を教えてもくれる。メタ視点を可能にするのは物語の要素のひとつだ。小説の中の登場人物が現実世界へと現れてくる『デス博士の島その他の物語』を論じた若島正のノートを引用しよう。
この物語が幻想小説として読まれうるのは、『デス博士の島』の登場人物たちがタッキーの現実世界へと侵入してくるからである。(…)虚構レベルの異なる二世界のあいだで境界侵犯が起こるこの現象は、ジェラール・ジュネットの用語を使えば、いわゆるメタレプシス(metalepsis)である。このメタレプシスによって、『デス博士の島』という書物が、タッキーの現実認識のあり方に影響を及ぼす。言い換えれば、『デス博士の島』はタッキーの現実世界に差し出された鏡に他ならない。
若島正『乱視読者のSF講義』「デス博士の島その他の物語」ノート p.239
「鏡」のモチーフは『零號琴』にも先に引用したものを含め、頻出する。<かがみのまじょ>、黒と金の万華鏡、美縟びとの想像を映し出す梦卑。「あしたもフリギア!」を書いた脚本家は語る。「物語はかがみがあなたを映し出すことで完成するのだよ」(P.570)と。
あとがきで作者はこの作品について、「「新しい」ものは、たぶんない」と言う。たしかにそうだろう。いつかの物語の焼き直し、再生産、二次創作、それらがふんだんに誂えられたこの作品は「新し」くはないのだろう。しかしその再生産でも、創造には変わりないし、真のオリジナルなんてこの世に存在しないと思っているので、私はそこは全く気にならないというか、この一文は作者の皮肉なのではないかと思っている。
ということで、『零號琴』は物語の体裁を採った一種の物語論としても読めるのではないか、というのが私の結論。
ものすごく長くなってしまった割にまとまりがあまりなく、ここまで読んでくださった方々には申し訳ない『零號琴』のレビューだが、どういう読み方をしたって面白いことには変わりないので、皆さんもぜひ。
<参考文献>
ジーン・ウルフ『デス博士の島その他の物語』
若島正『乱視読者のSF講義』