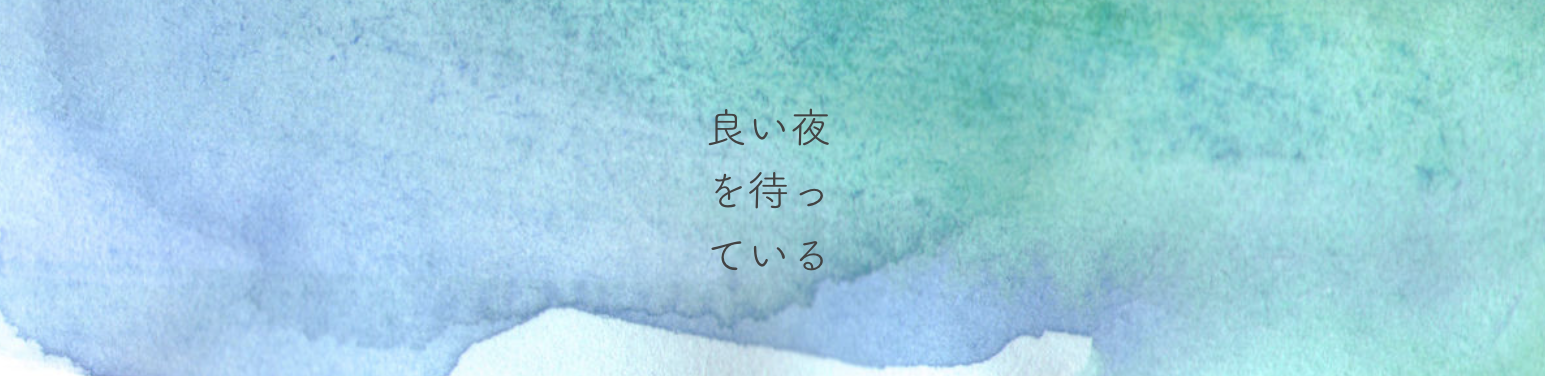俺たちの住むこの国は、バーガー調理係、ブリトー調理係、タコス調理係、カクテル係、無愛想なレジ打ち、介護人、犬の散歩屋、看板を振る自由の女神、路上生活者、あるいは物乞いたちの国になった。 俺にはちっとも超大国のように聞こえない。
p.287 「戦争とリベラル・アーツでまわるカーライル」
沈みかけたハリボテの船に乗っているのはアメリカだけではなく、日本も同じだ。
私たちの住むこの国は、コンビニ店員、9時から23時までワンオペで営業する牛丼屋、愛想を振りまかないとそれだけで文句を言われるレジ打ち、路上生活者、あるいは病院にも行けない孤独な老人たちの国になった。私にはちっとも超大国のように聞こえない。
大学に行くのに多額の借金を重ね、職につけばセクハラ・パワハラに苦しむ。自殺国家、痴漢大国、賃金は増えず税金だけで年収のほとんどを持っていかれ、カントリーマアムはどんどん小さくなっている。あと最近レイプが合法になった。
経済大国の看板はもうとっくに錆びて崩れかかっているのに、それを下ろすことは国のプライドが許さないらしく、どんなにその影でつつましく暮らす人々が貧困や病気や介護で苦しもうと、そこに払う金よりも看板を建て直す費用が優先される。
そんな国が、私の生まれた国で、今でも住んでいる国だ。私はこの国を出たことがない。
冗談のように聞こえるかもしれないが、これは冗談なんかではない。なぜなら俺は冗談を言うタイプの人間ではないからだ。
p.209 「トリシティーズの農場事情」
私もまさかこんな国に住んでるとは思わなかった。冗談だったらよかったのにね。
この本では著者リン・ディンがアメリカ各州を巡り、そこに住む所謂「底辺の人々」、ホームレスや日雇い労働者、アル中、薬中、障害者たちと話をし、一緒に一杯の安いビールを飲む、ときに奢り、ときに奢られながら。
リンが描き出すのはアメリカという超大国の底辺だが、日本でもほぼ変わらない光景が見られる。人々は目の前にある苦難から目をそらすために安ビールを買ってしまうし、街灯に引き寄せられる蛾のようにパチンコ屋に吸い込まれていく。何も考えなくて良いように。ときに通勤途中の中央線にも吸い込まれていく。何かを考えたところで何も良くならないから。だからここに書かれている光景は、背景の巨大ショッピングモールの廃墟やだだっ広い道路を日本のションベン臭い路地や隣家との間が2cmしかない極小住宅に変えてしまえばそのまま「これ日本のことじゃん」と読めてしまう。ニュージャージー州もカリフォルニア州もすぐ隣りにある。
破産しているのに、ロブは毎日バーにやってくる。そしてビールを買うために20ドル使う。ちゃんとチップをあげていたら、たったの5杯しか飲めない。ロブは1日にL&Mを2箱も吸うので、追加で10ドル50セントかかる。「でも、ただ家でじっとしてるなんでできねえよ。外に出てきて、話をしなくちゃ。どうしたらいいっていうんだよ」
p.185 「レヴィットタウンをさまよう」
リンはアメリカを旅するときに、車は使わない。鉄道や長距離バス、徒歩で移動し、その道すがら出会った人々と話をする。よう、ビールでも飲むかい?そいつは大変だったな、それで娘さんはその後どうなったんだ?そうか、でもまだ良かったよ。あんたには家もあるしな。
その語り口は軽快で心地よくて、「ああこんな人に話しかけられたらついベラベラ喋ってしまうな」と思う。
リンは人の話を聞くのがとてもうまい。くど過ぎない程度にリアクションをし、反感を買わない絶妙な力加減で同情し、相手の「そうだろ?」を引き出し、気持ちよく話をさせる。コミュニケーション力の鬼。グイグイと彼らの話を引っ張り出していく。それでいて、湿っぽすぎないし、ドライすぎるわけでもない。「人情」と「批判的な視点」のバランスがとても良い。
兎にも角にも、本当にたくさんの「底辺の」人々が出てきて名前も覚えきれないくらいなのだが、一番印象に残ったのはジリアン。通称ジル。彼女はオークランドの路上で暮らしている。
薄い掛け布団で身を包んだその女は、中腰になって地面から何かを拾っていた。最初は、タバコの吸い殻でも集めているのかと思ったが、すぐに彼女が歩道にくっついていないものなら何でも拾っていることに気付いた。紙切れ、枯葉、マッチ棒、キャンディーの包み紙・・・・・・彼女はそうしたこまごましたものを拾うだけでは満たされず、コンクリートの上に跪いて、拾ったものを配列し、それらに秩序と意味を与えていた。
p.39「オークランドの狂気」
彼女とリンの話は噛み合わない。ジルは頭の中で毎日ママと会話している。
そして、リンに緑色の錠剤をひとつくれる。リンはその錠剤を飲む。
ジルが自分の体と口に入れていいと思っているものを拒否するのは失礼だろ?それがフクロネズミだろうが、ノネズミだろうが同じだ。アメリカの若者は、先輩たちのせいでめちゃめちゃになった不条理な現在と、舵を失った未来を耐え抜くためにクスリを摂取しないといけないと感じている。
P.41 「オークランドの狂気」
彼女はまだオークランドで物を拾い続けているのだろうか。その配列にはどんな意味があるんだろう。物と会話したりもするのだろうか。そのストーリーを、私はいつか聞いてみたいと思う。どうか彼女が身にまとう毛布が温かでありますように。
リンが話を聞いた人々の声は、街の喧騒に紛れてきっと誰にも届かない。本当にたくさんの、たくさんの人生のカケラが散らばっては風で吹き飛ばされるのを繰り返す。
何か変化を起こせればと思ってこの本にある一連の文章を書いた。でも、変わったのは俺の人生だけだった。
p.1 「日本の読者へ」
そうだよ、何も変わらない、でもリンは書いた。そして私たちはそれを日本語で読んだ。
誰にも届かないはずだった声は、日本まで届いている。それは確かな「変化」だと思う。