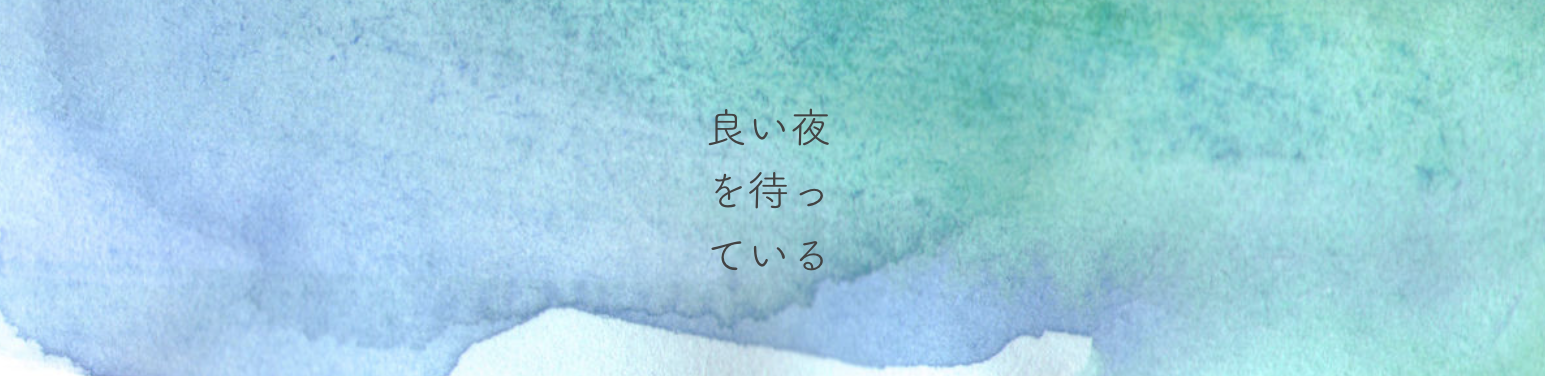池澤夏樹編の『世界文学全集』にも収められているボフミル・フラバルの代表作がこのたび文庫化!ということで、わたしにとっては初のフラバル作品。
この作品はチェコで働く若き給仕、ヤン・ジーチェが百万長者を目指し、エチオピア皇帝に給仕するまでに上り詰め、そして戦争があり、老いて自身の半生を振り返るまでの物語。一歩ずつ夢を叶えていく中で出会った人々の様子や、おかしなエピソード、悲しい別れ、戦争の痛みなどがユーモラスな文章で綴られている。
5つの章が連作短編のようになっており、5つとも「これからする話を聞いてほしいんだ。」からはじまり、「満足してくれたかい?今日はこのあたりでおしまいだよ。」で終わる、読者に語りかけるような形式となっている。
彼が送った人生の中でのエピソードはひとつひとつが絶妙なほら話のようだ。コツコツと副業(ソーセージを高値で売るという割とせこいやり方笑)で稼いだ金で娼館に通っては女性の下腹部を花で飾る妄想にふけり、燕尾服を仕立てに行った先では胴体模型が雲のようにふわふわと天井に浮いていたり、愛人と「子どもの部屋」でぬいぐるみに囲まれて過ごす大統領を目撃したり、おかしなエピソードは挙げればきりがないほど。エロティックな描写も多いが、甘美なロマンティックさがあるというよりはドタバタ喜劇の様相を呈している。しかし、面白おかしいことばかりではない。富裕層が酒池肉林で豪遊する様を、給仕ならではの観察眼で見つめるジ―チェは、百万長者を目指しながらも、富の持つ一種の欺瞞性にも気づいている。
ここホテル・チホタでわたしは気づいた。労働が人間を高尚にすると考えたのは、ここできれいな娘たちを膝に乗せて一晩中飲んだり食ったりしている人たちにほかならず、それは子どものように幸せになれる豊かな人たちなのだと。そしてわたしは、豊かな人達は呪われているか、どうかしていると思った。(・・・・・・)田舎の家屋にいるのがいかに幸せかといったたわ言はうちに来るような客人たちが考え出したことで、とどのつまり一晩で湯水のように金を使い、東西南北に紙幣を投げ捨てていい気分になっているかれらには、本当はどうでもいいことだったということが、今わかった。
p.87「ホテル・チホタ」
裕福な人間が、貧しいけれど働き者の人々を称賛し、「幸せものだ」と勝手に定義してストーリーを作り上げていく様子は、わたしもさんざん、現実世界で目にしてきたし、実際わたしも貧しい側の人間なので、この苦々しい気持ちはすごくよくわかる。
自分たちが称賛する仕事を夢見心地で眺めるのだが、かれらは決して自分から同じ仕事をしたことなどなかった。もし同じ仕事をしたら、不幸と感じ、幸せなどと言ってはいられないだろう。
p.88「ホテル・チホタ」
幸せか不幸せかを判断するのは自分でしかないのに、他者に三文小説のように消費されてはたまったものではない。ジ―チェはおそらく、それが嫌だったからこそ、百万長者を目指したのではないか。「百万長者になったら幸せになれる」ではなくて、「幸せかどうかを自身で判断するために、百万長者になってから確かめてみる」という姿勢だったのではないかと、わたしは思う。
そして戦争。ドイツからナチスがやってきて、否応なく彼も戦争に巻き込まれていく。愛する人を失い、老いてはじめて芸術に触れ、感化されて半生を振り返りながらこの物語を書き終える、というラストなのだが、後半はやや首を傾げてしまった。精神障害を抱えた息子を(おそらくは病院へ送り込んでそのまま)ほったらかし、自分は芸術に目覚め、動物と自然に囲まれ、肉体労働をしながら満ち足りた内省的な暮らしを送る、というのはなんとも都合がよすぎやしないか。
解説を読むとフラバルはケルアックの『ダルマ・バムズ』にある森林観察員の場面をとても気に入っていたようで、そのような美しい場面を描きたかったのかもしれないが、どうもラストだけが浮いて見える。とても静かで美しいのは間違いないのだが、さんざん、荒唐無稽ともいえるエピソードを並べてきて、突然精神的な方向へ一気に舵を切られたのでやや面食らったし、「数奇な人生であった・完」で良いのか?という気持ちに・・・。息子はどうしたんだよ・・・。
まあ、ラストはともかくとしても、「給仕」という仕事ならではの観察力や語りの魅力は確実にあって、引き込まれる文章であることは間違いない。
読者に語りかける形式の文頭と文末は、解説にある「パービテル」の語りを表象しているのだろう。
「パービテル」というのはフラバルの造語で、もとは19世紀の詩人が「タバコを吸う」という意味のpalitをもじってpabitとしたのが始まり。その後フラバルが「色々な話を吐き出す」「滔々と話をする人」の意味で「パービテル」という言葉を作ったそうだ。フラバルによると、「パービテルはたいていほとんど何も読んだことがないが、その代わりによく見て、よく聞いている」。様々なエピソードが次から次へと溢れ出してくる様子は「パービテル」の語りそのものだ。
この作品は、色々な読み方ができる作品だと思う。戦争文学とも読めるし、成長小説でもあるし、おとぎ話のようでもあるし、少しおかしな愛の物語でもあるだろう。グロテスクで露悪的な描写も少なからずあるので、エログロアンテナをお持ちの方のツボにもハマるかもしれない。もちろんお仕事小説として読んでも面白いだろう。
余談だが、この本を読んでいる最中、「今は英国王に給仕しているので他の本は我慢」「さて今日も通勤途中、英国王に給仕しますか」とひとりごちていたのは楽しかった(実際にジ―チェが給仕したのはエチオピア皇帝なのだが。なぜこのタイトルになっているかは読んでのお楽しみ)。
君もこの夏、英国王に給仕してみないか?(夏の河出文庫販促キャッチコピー)