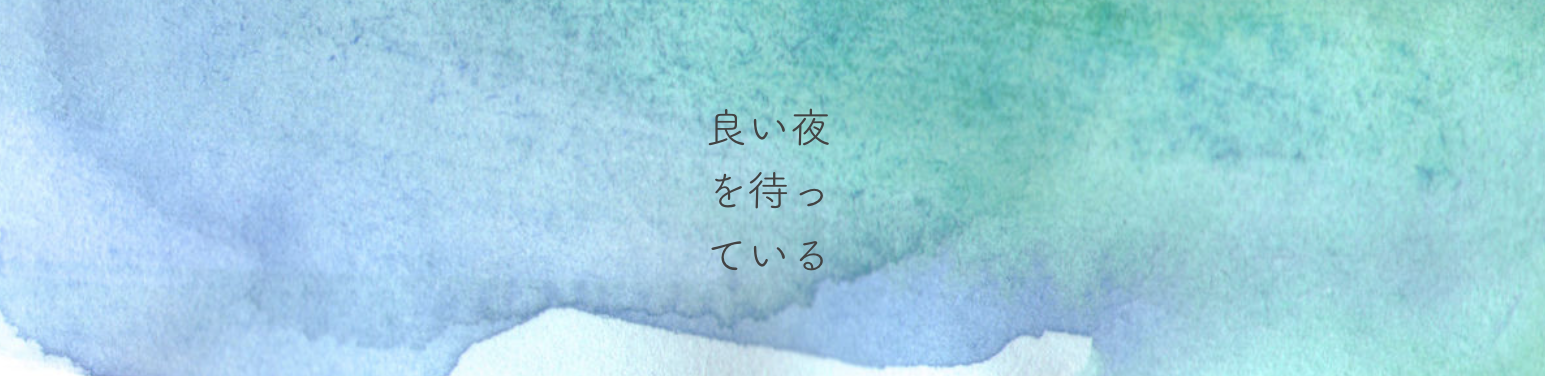写真や映画を見たとき、「ああ、この瞬間を切り取るとは!」とその鮮やかさにハッとする時がある。映像だととくにそれが顕著だが、文学でもその瞬間はあって、まるで新鮮な果物を研ぎたての刃物で半分に切ったときのような、毛羽立った表面からは想像もし得ない艷やかな断面にドキッとする時がある。
ルシア・ベルリンを読んで一番に感じたのはその「切り口の鮮やかさ」だった。
ルシア・ベルリンの小説は帯電している。むきだしの電線のように、触れるとビリッ、バチッとくる。読み手の頭もそれに反応し、魅了され、歓喜し、目覚め、シナプス全体で沸き立つ。これこそまさに読み手の至福だ――脳を使い、おのれの心臓の鼓動を感じる、この状態こそが。
p.292「物語こそがすべて」リディア・デイヴィス
描かれているのは、彼女が暮らした「物語」だ。
私小説の部類に入るのだろうが、私がいままで読んできたどの私小説よりも彩り豊かであった(そもそも私小説はあまり好んで読まず、パッと思いつくのが太宰治、芥川龍之介、藤枝静男、西村賢太あたりなので偏りがあるのはご容赦願いたい)。私小説らしからぬ私小説で、私は訳者あとがきやリディア・デイヴィスが寄せた文章を読み初めてこれが私小説だと知った。
<実際のできごとをごくわずか、それとわからないほどに変える必要はどうしても出てくる。事実をねじ曲げるのではなく、変容させるのです。するとその物語それ自体が真実になる、書き手にとってだけでなく、読者にとっても。すぐれた小説を読む喜びは、事実関係ではなく、そこに書かれた真実に共鳴できたときだからです。>
事実を捻じ曲げるのではなく、変容させること。
p.307「物語こそがすべて」リディア・デイヴィス
ひとつひとつの作品はとても短く、それでいてバリエーションがとても豊かだ。これは彼女の人生が波乱万丈であったことにも由来するのだろう。
アメリカ西部の鉱山町から転々と住居を移し、様々な職に就き、身分も変わり、結婚をし離婚をし、依存症も経験し、子を育て、家族の介護に明け暮れる日々を過ごしながら彼女は書いた。その物語それぞれの切り口がとても鮮やかで、いちいちハッとしてしまうのだ。「そこでそう来るか〜」「あ〜もうこの感じ!!知らないのに超知ってる!!」と頭を抱えてしまう。もちろんいい意味で。
表題作では、主人公はバスに乗りあちこちの家を掃除しに行く掃除婦だ。彼女は行く先々で、ちょっとしたもの(睡眠薬やマニキュア、香水、トイレットペーパーなど)をくすねたり、もらったりして、仕事仲間と笑ったり、ユーモラスな「手引き書」を考えたりしながらバスに揺られていく。
(掃除婦たちへのアドバイス:奥様がくれるものは、何でももらってありがとうございますと言うこと。バスに置いてくるか、道端に捨てるかすればいい。)
p.48
(掃除婦たちへ:猫のこと。飼い猫とはけっして馴れあわないこと。モップや雑巾にじゃれつかせてはだめ、奥様に嫉妬されるから。だからといって、椅子からじゃけんに追い払ってもいけない。反対に、犬とはつとめて仲良くすること。着いたらすぐ、チェロキーだかスマイリーだかを五分、十分となでてやる。便座のふたは忘れずに閉めること。顎の毛皮からしずくがしたたる。)
p.53
彼女の思考はとりとめなく、あちこちに飛ぶが、恋人の死だけは頭の片隅に固定されている。通りの落ち葉を見つめながら、紅茶を入れ、勤め先の主人と話しながら、パズルのピースを探しながら、死んだ恋人を想う。この感覚、何かを失ったことのある人ならわかると思う。表面はなにもかも諦めたように振る舞い平然と仕事をし、笑ったりもするが、喪失の部分だけがいつまでも消えない焦げつきのように、残ったままになっている感覚。
40番―テレグラフ―バークレー行き。
(……)わたしのバスが来る。テレグラフ通りをバークレーまで。マジック・ワンド美容院のウィンドウには、ハエタタキの先にアルミホイルの星をつけた魔法の杖(マジック・ワンド)。お隣の義肢ショップの店先には、お祈りのポーズの両手、それに脚が一本。
ターは絶対にバスに乗らなかった。乗ってる連中を見ると気が滅入ると言って。でもグレイハウンドバスの停車場は好きだった。よく二人でサンフランシスコやオークランドの停車場に出かけていった。いちばん通ったのはオークランドのサンパブロ通りだった。サンパブロ通りに似ているからお前が好きだよと、前にターに言われたことがある。
ターはバークレーのゴミ捨て場に似ていた。あのゴミ捨て場に行くバスがあればいいのに。
p.56-57
頬杖をついてバスの窓から道路で舞う落ち葉や雪を眺めながら「手引き書」の言葉を、行きつ戻りつする思い出を、ぼんやりと考える彼女の姿が目に浮かぶ。
それはいつかの私のようでもあり、どこかで読んだ本の情景でもあり、ルシア・ベルリンその人でもある。
この作品集にはたくさんのわたし(たち)がいる。そう思わせてくれる小説は、良い小説だ。時代を超えて共鳴する真実というのは確かにある。それがルシア・ベルリンが言っていたことなのだとしたら、ここにはその真実があると思う。
「あたしはあんたの内面なんか屁とも思っちゃいない。あたしは文章の書き方を教えに来てんの。あのね、嘘をついたつもりが真実を語っていた、ということもあるのよ。この話はよくできてる。どんなふうに書かれたんであれ、ここには真実がこもってる」
p.245「さあ土曜日だ」
彼女の作品には死の臭いが色濃くある。病気で死にゆく妹との病院での生活や、母親、アルコール依存、刑務所での講義など、描かれる光景は様々だが、「残された側」の生活を彼女はこれでもかと鮮やかに切り取っていく。連続体である人生のスナップショットを言葉で撮っていく。
わたしはサリーが死んでしまうことに怒っているんだろうか。それでこの国に八つ当たりしているんだろうか。こんどはトイレが壊れた。もうフロアごと外に持っていってもらうしかない。(・・・・・・)
死には手引き書がない。どうすればいいのか、何が起こるのか、誰も教えてくれない。
p.183「苦しみの殿堂」
人が死ぬと時間が止まる。もちろん死者にとっての時間は(たぶん)止まるが、残された者の時間は暴れ馬になる。潮の満ち引きも、日の長短も、月の満ち欠けもお構いなしだ。(・・・・・・)何よりつらいのは、また元の生活に戻ったとき、日々の習慣も記念日も、何もかもが空疎なまやかしに思えてくることだ。すべては人をあやし、なだめすかして、粛々と容赦のない時の流れに押し戻そうとするペテンなのではないかと思えてくる。
p.258-259「あとちょっとだけ」
本当にどの作品もしみじみと良くて、リディア・デイヴィスのこの言葉そのままである。
ルシア・ベルリンの文章ならば、私はどの作品のどの箇所からでも無限に引用しつづけ、そしてしみじみと眺め、堪能しつづけていられる。
p.309 「物語こそがすべて」リディア・デイヴィス
この作品集で見た景色をきっとときどき思い出すだろう、バスから眺めた汚い道路を、救命病棟に運び込まれた騎手のことを、死んでしまった刑務所の囚人生徒たちの顔を、アルコールから離れられなかった元夫のことを。
この記憶に残る鮮明さ、どこかで知っている・・・と思って考えていたら、小中学生のときに読んだ吉本ばななの作品で経験した鮮やかさだとふと思い出した。『TSUGUMI』で見た熱海の海や、『キッチン』で足の裏に感じた、冷たく薄汚れたキッチンの床。いまもありありと思い出せるその情景と同じように、ルシア・ベルリンの作品もいつか思い出すだろう。それが私の「真実」だから。
この作品集は、私が(ルシア・ベルリンほど波乱万丈ではないがまあ並程度に辛酸もなめてきた)中年女性だからこそ刺さる部分も多いなと思っていて、若者が読んだときにどのように感じるのかとても興味がある。
読んだ方はぜひ感想を教えてほしい。