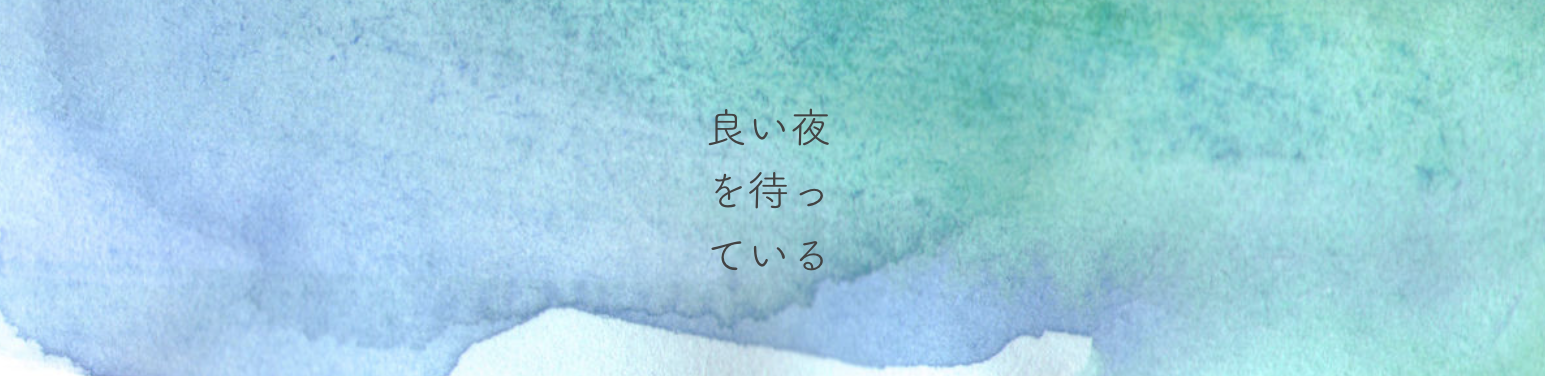ひとことで言うと、変な小説。
ただ、「変」とは言っても、芸術への情熱に裏打ちされた「変」さに、私は惹きつけられる。
そんな小説だった。
あらすじは、こんな感じ。
30歳非モテ青年がいきなり男子校にぶち込まれ、そこで起こるなんともバカバカしい諍い(「顔つきくらべ」???)に巻き込まれつつ、これまたいきなり連れて行かれた下宿先のギャルにひと目惚れして彼女を覗き見しつつ妄想大爆発、かと思えば作者の小説論が挟み込まれ、S極N極のような教授2人の決闘、果てはBLからの田舎のお嬢さんとの駆け落ち・・・。
これを奇書と呼ばずになんと呼ぼうか、と感じてしまう、間違いなくぶっ飛び系の作品。なのに、飽きずにぐんぐん読んでしまう。ただ小説で無茶苦茶をやっているだけではなくて、シンメトリーになった構成や言葉のリズム、緩急の付け方、読者を食ったようなラスト・・・と作者の力量がきちんと根底にあるのがわかる。
また、訳文がとにかくすごい。こんなにバカバカしいのに、品性を保ちつつ格調高い文章で滔々と語りだすかと思えば「おちり!おちり!ふくらはぎ!」の連呼。勢いよく転がって展開する勢いのあるふざけ倒した文章と、自嘲を交えた「永遠の青二才」(≒厨二病)特有のわざとらしい美辞麗句、冷静に俯瞰する批評のバランスを、よく日本語に落とし込んだなと。訳は米川和夫さん。偉業です。
この作品はただ単にバカ小説(褒め言葉)として読んでも、ゴロンゴロンと転がってゆくボールを追いかけるような楽しみがあってやめられない。その楽しみ方に加えて、付録(スペイン語版が出版されたときの序文や、雑誌への寄稿文)を読むとよく分かるのだが、作者のいわゆる古典的、芸術と称されてきた形式へのアンチテーゼ、真摯な反逆行為という側面もある。
※本編内でも作者の意図については2章に渡って触れられているのだが、私には小難しくてよくわからなかった。
ゴンブローヴィッチはデビュー作を未熟と評されたことを逆手に取って、この作品を書いたらしいが、おちり小説(?)をこの精度で書き上げてしまうのはすごい。熱狂的なファンがいるのもよく分かる。
未熟は、いいかえるなら、若さ、低さ、愚かさということにもなり、むろん、成熟、不惑、賢さと対立する観念だ。完成にたいする未完成、調和にたいする混沌が未熟である。もとより、人は高さを、完成した形式をもとめてやまぬものだが、と同時に、それに反撥し、正反対の方向にひかれるもの。なぜなら、完成は死を意味し、未完成はそのうちに無限の可能性をはらんでいるからである。未熟さは、力だ。
(「世界の文学」版訳者解説 P.499)
未成熟・未完成なものは、いうほどマイナスなものではない。未完成ゆえの、無限の広がりは、あるのではないだろうか。
少し話がそれるが、つい最近、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」を観た。
※記事の公開日時が2/13となっており、この時期に劇場版は公開されていないのですが、この本を読み終わった日付なので、ご了承ください。
20年以上も続いた、少年の未成熟さ、大人の幼稚さをめぐる宇宙規模のカオスな戦いに終止符が打たれたのだ。作品が完成したこと、ある着地点を庵野監督をはじめとするエヴァンゲリオン制作陣が見出したこと、それはいちファンとして、とても喜ばしくもあり、また、ひどく寂しくもあった。ミサトさんは作中、「すべてのカオスにケリをつける」と言っていたが、それはつまり未成熟(=混沌)を脱し、大人になる(なってしまう)ことだ。永遠に同じところをぐるぐる回っていると思っていたエヴァは、その未完成さでも私達を楽しませてくれていたんだと、終わってやっと気づいた。混沌から出られてよかったと、心から思う。でも、出口が分からず右往左往する楽しみも、あったのだ。もちろんそれは、苦痛も伴うが。
ゴンブローヴィッチがフェルディドゥルケファン、すなわちフェルディドゥルキストへ向けた手紙が巻末に収録されている。そこには、芸術を志す人々、芸術を愛す人々への、ゴンブローヴィッチらしいエールが書かれている。
フェルディドゥルキズムとは創造意欲のことにほかならないのです。芸術は「創造」すべきものだと要求してみせてこそ、フェルディドゥルキストです。ですから、くれぐれも希望を失わないでいただきたい。
(フェルディドゥルキストへの手紙 p.520)
フェルディドゥルケは最後の最後で、「読んだやつ、バーカ!」みたいなことを言ってくるのだが、これは半分くらい、ゴンブローヴィッチの照れ隠しだと私は思う。だってこんなに熱いエールを書くような人が、フェルディドゥルケを楽しんだ人たちを反故にするわけないのだから。
「とても気に入った」だの、「魅かれるものがあった」だの、それが真摯で率直な感想であればあるほど、そんなことばを聞かされる者も、口にする者も、揃って赤面するハメになる。だから口をつぐんでいて欲しい。お願いだ。口をつぐんだまま、よりより未来に夢を託して欲しい。とりあえず、もし気に入ったことをぼくに伝えたいなら、ぼくを見掛けた際でかまわないから、ご自分の右耳を触ってくださるだけでいい。
(フェルディドゥルキストへの手紙 p.515)
謙虚かよ。ごめんねゴンブローヴィッチ。たくさん書いちゃった。
ラストの一文にはきっと、「だよね!でも書いたやつもバーカ!」と右耳を触りながら返して、一緒に笑うのがいいのかもしれない。