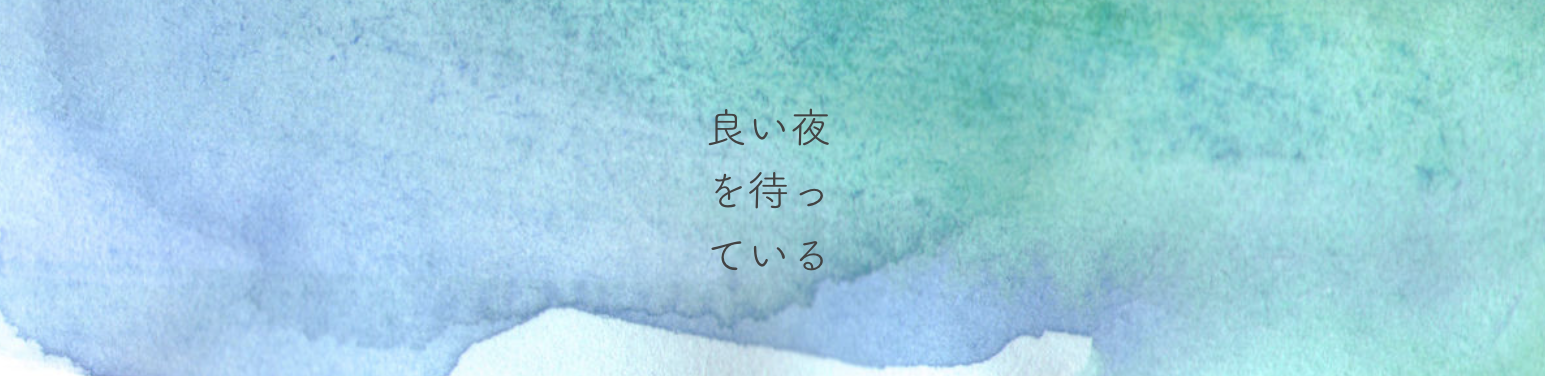グリオールは巨大な竜。その大きさは背中までの高さが750フィート(約228m)、長さが1マイル(約1.6km)ほどもある。かつて魔法使いがグリオールを殺そうとして失敗し、完全に殺すことはできなかったものの、竜の身体は麻痺して動かなくなった。何千年もの時をかけ、表皮には木々が生い茂り川が流れ、竜の身体は巨大な森のようになっていった。背中には人々が集まり、いつしか村ができ、竜の鱗やそこに生える植物で商売を始め、口腔内にも社会からのはみ出し者たちが巣食うようになっている。しかし、竜の霊気は衰えず、人々の意識に影響を与え続ける。竜はまだ、ゆっくりと成長を続けているのだ・・・。
というのが、この「グリオール」シリーズの世界設定。
本作には、グリオールに翻弄される人々を描いた4つの短編が入っている。
舞台設定だけでもだいぶワクワクする内容ではなかろうか!!
竜と戦ったり、竜が仲間になったりするのではなくて、竜そのものはほとんど動かず、恐れながらも竜を生活の糧として組み込んでしまった人間の業と知恵、人間同士の関係性や、竜を中心として生まれた人間社会にフォーカスを当てているのがとてもユニーク。
そもそもグリオールの「影響」が具体的にどんなものなのかははっきりと分かっておらず、村の人々が陰気だとか、鱗にほど近い場所で生まれたため美貌に恵まれているとか、幻が見えるとかいうもの。必ずしも悪い影響だけではなさそうなところも、例えば海や月の満ち欠けのような「科学的に証明されていることもあるけれど、それだけでは説明のつかない、巨大で不気味だが神秘的でもあり、人間を惹きつけて止まない存在」と同じなのかもしれない。
ただ、自由と支配、意思と強制、環境と人間、社会と個人、行為と責任という、我々の存在の根源に関わる問題を、生々しいイマージュとして提示し、ここまで切実に身近に感じさせる小説は滅多にあるものではない。グリオールという存在を設定することでそれが可能になっていることは言うまでもない。ファンタジィとは本来このように作用する。そしてシェパードの作品のどれにも通底する性格でもある。どの小説にあっても、超自然的存在やシチュエーションは、あまりに大きすぎるので直視するのを普段は避けている問題を、あらがいようもなく、突きつけてくる。
(解説 p.416)
以下、4作それぞれの感想を。
■竜のグリオールに絵を描いた男
表題作は今年バカ売れした傑作SF短編集、伴名練『なめらかな世界と、その敵』の中に収録されているこれまた最ッ高!!!な傑作、「ひかりより速く、ゆるやかに」の数ある元ネタのひとつ。わたしは伴名練の方を先に読んでいたので、「これがこう化けるのか、やられた!!」という気持ち良さがあった。
多分逆なら逆でニヤけながら読めるはず。かつての魔法使いが殺し損なったグリオールを、竜の皮膚に絵を書くことで、絵の具の毒で殺していこうとする画家の物語。
これだけ、その画家についての研究書からの引用、というメタ要素が入っているのだけれど、この設定は早々に止めたようで(笑)、その後の作品には出てこない。初志貫徹頼むよ、とも思ったけれど、その設定がなくても十分楽しめたので良しとする。
■鱗狩人の美しき娘
とある事件によりグリオールの口腔内に逃げ込んだ美しい女の半生。当初は元の世界に戻れないことに気落ちして鬱状態だった彼女が、次第に生物学・植物学的なところからグリオールの体内の観察に興味を持ち始め、知識欲に突き動かされ、生命力を取り戻していく様子は、やはり人間は知識欲がないとダメだなと思い知らされる。わたしも日がな一日寝ていないで勉強しよ。なかなかに官能的な箇所もあって、住んでいるところが粘膜なだけあるなあと(?)。彼女がグリオールから抜け出せるのか、そこで一生を終えてしまうのかが気になって仕方なくて、ぐんぐん読み進めてしまった。
■始祖の石
グリオールの皮膚から形成された石をめぐる、宝石研磨師の男とその娘の愛憎にミステリとカルト宗教の風味を加えた一品。
娘ミリエルが非常に蠱惑的で惹き寄せられてしまう。ラストがわたしはいまいち気に食わないが、ちょっとしたトリックもあって楽しめる。
■嘘つきの館
グリオールが子供を欲しがり、女に化けた竜がグリオールの性質を持つ人間の男と交わらせ、子を成すというお話。異形との禁忌の愛・・・というとロマンチックなようだが、竜(女)と男との間にあるのは、男が期待した慈しみや愛情ではなく、ただ暴力的で動物的な繁殖への欲求。
本書は全体的にエロティックでバイオレンスな描写もそこそこあって、この作品が一番バイオレンス味が多かった気がする。竜の理不尽さというか、人智を超えた「暴力」がガツンと読者を叩きのめす感じ。この作品がわたしは一番好きかな。
どれをとっても竜の目に見えない圧倒的な力に翻弄される人間たちの生き様や、竜自身が大地と一体となり動植物を育んでいく美しさが堪能できる素晴らしいハイ・ファンタジーとなっている。
ということで、本書を読了してから感想を途中でほったらかしていたら続編も出版されてしまった(うれしい!)。
こちらも読むのがとても楽しみ。