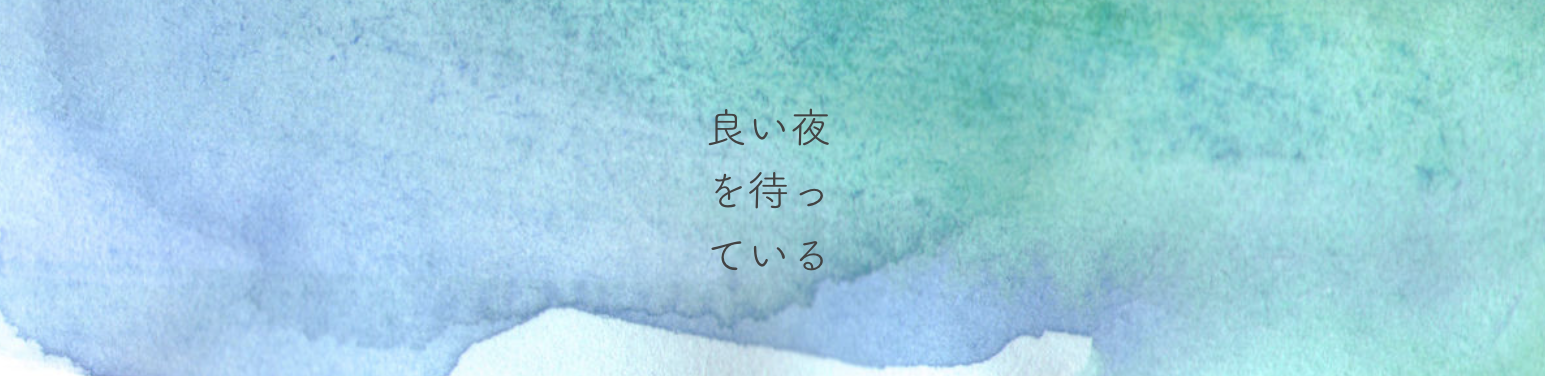夜熟睡しない人間は多かれ少なかれ罪を犯している。
彼らはなにをするのか。夜を現存させているのだ。
夜を愛し、夜に呪われている人々へ
寝苦しい夜にふとどこからか吹いてくる、色々な匂いをはらんだ風。
それは隣家のカレーのにおいだったり、大学生の焚く安っぽいお香のにおいだったり、好きな人がベランダで吸うのタバコのにおいだったり、新しく赤ちゃんが生まれた家族がワイワイ入っているお風呂のシャンプーのにおいだったりするけれど、総じて思い出すときにはなんだか切なく哀愁をはらんだものとなる。
モリス・ブランショの引用で始まるこのお話は、夜がずっと続けばよいのにと願い、夜が明けても「いや、まだ夜の続きでしかないはず」と浅く呼吸を繰り返す夜更かしの民たちの鼻先をかすめていく、異国のにおいを運ぶ風のような物語だ。
とにかくにおう
こう書くとなんだか上述のセンチメンタルが台無しになってしまうが、この作品で私が一番感じたのはそこから立ちのぼる数々の「におい」だった。
いなくなった友人を探してインドを旅する男が出会う様々な人・風景・できごとが無駄のない筆致で幻想的に描かれてゆくこのお話は、とにかくあらゆる場面で多種多様なにおいがするのだ。
たとえばこれ。
男が訪れた病院(とは名ばかりの、ゴキブリだらけ・壁のシミだらけの至極劣悪な場所)での一場面。
天井からはいくつかの薄暗い電球が下がっていて、中に入ったとたん、僕は棒立ちになった。匂いがひどかったのだ。入り口のドアのそばには、粗末な衣服をまとった男が二人、しゃがんでいたが、僕たちが入っていくと、むこうに行った。
「アンタッチャブルです」と医者は言った。「病人のしもの世話をするのです。他の階級にこの仕事をするものはいません。インドではそういうことになってるのです」
とっつきのベッドにはひとりの老人が寝ていた。素裸で、がりがりに痩せていた。巨大なペニスがくしゃくしゃになって腹の上にあった。医者はその男に近づき、額に手をあてた。口に薬を入れてやったように思えたが、ベッドごしに見ている僕には、はっきりわからなかった。「この人はサードゥです」医者が言った。「彼の生殖器は神に捧げられています。むかしは不妊の女たちにあがめられていましたが、本人は生まれてから一度も、生殖にたずさわったことがないんです」壁はベテルの実を噛んで吐きつけるために、赤いしみだらけで、息がつまりそうに暑かった。僕を窒息しそうな気分にさせたのは、あのひどい悪臭だったのかも知れない。どっちにしても、天井の扇風機は止まっていた。
(p.34-35)
読んでいるだけで、人間の垢やら排泄物やら薬のケミカルな臭いやら、病人特有の物悲しさ・痛み・諦め・仄かな希望を煮詰めて三ヶ月放置したみたいな息の匂いやらでこっちまでウップとなる。それを淡々と、本当に風のようにさらりとした肌触りで書いてしまうタブッキの凄さよ。
たとえばこれ。
教会を訪れた際、会う約束していた神父を待つ間に案内された図書室。
中は広々とした、涼しい部屋で、閉めきった匂いがこもっていた。本棚にはちぢれ模様のバロック装飾があって、象嵌がほどこされていたが、かなり傷んでいるようだった。部屋の中央には、捻れ飾りの脚がついた細長いテーブルが二つ、壁際には小さい低いテーブルがいくつか、そして教会用のベンチと籐の古びたひじかけ椅子が何脚かあった。むかって右側の本棚に目をやると、 教父学の本が数冊、さらに数冊の十七世紀イエズス会の記録が注意をひいた。
(p.100)
古書店や図書館でにおう、埃と古い本のカビ臭さと、宗教施設独特の、なんだか鼻をつくようなツンとしたにおい。教会や寺院を訪れたことがある人はわかると思うのだけれど、宗教関連の施設、特に歴史の古いものには独特のにおいがある。お香や蝋燭やお線香だけではない、祈りと哲学と死の濃密なにおい。
このあと男は本を読みながらウトウトして悪夢を見るのだが、私はこの古書と宗教臭のコンボが悪夢を引き起こしたんじゃないかと思っている。
ほかにも、未来を占う奇形の兄が顔をうずめて嗅ぐ弟の髪のにおい、川沿いのホテルで飲む安いワインのにおい、死にゆく男と汽車を待つプラットフォームで吸うインド煙草のにおい。直接においに言及している訳ではなくても、こんなにもにおいを漂わせて幻想と現実のあわいに引きずり込んでいく作品は、そうそうないのではと思う。
とにかく粋
幻想的でうっとりするだけじゃない。会話の端々や、登場人物が見せるユーモラスな仕草がとにかく粋なのだ。語彙が少なくて粋としか表現できないのが歯がゆいが、カッコイイでもなくてキザでもなくてとにかく粋なのだ。
前述した病院で、医師との別れる際の一幕。
「私の名はガネシュです」と彼は言った。「象の顔をした快活な神様とおなじです」
別れぎわに、僕も自分の名をつげた。そこから鉄門の出口までは、ジャスミンの繁みをへだてて数歩の距離だった。門は開いていた。僕がふりむいたとき、また彼は言った。
「もし、その方にあったら、なにか伝えましょうか」
「いや、けっこうです」僕は言った。「なにも言わないでください」
彼はまるで帽子をとるように、かつらをはずし、僕にむかってかすかに頭を下げた。通りに出ると、夜が明けはじめていて、歩道の人々がそろそろ目をさます時間だった。
(p.38-39)
だんだん明るくなり音が増え始める早朝に、静かにかつらをあげて挨拶する医者。ここを読んだとき、思わずクスっとなってしまった。きっとインドは朝でもむっとする暑さなはず。そのなかで目をしぱしぱさせながら感じる朝日の眩しさと(きっとこちらも眩しい)医者の頭と、大きくなってゆく街の雑踏の音が楽しい。
お話のラストにおける、男と女の会話も本当に素敵で、一字一句写経したいくらいなのだけれど、一応ネタバレにもなるからここには一部だけ引用させていただく。
「あなたの本にはなにか納得のいかないところがあるわ」とクリスティーヌが言った。
「なんだかわからないけど、どこか納得がいかない」
「僕もそう思う」
「いやあね」クリスティーヌが言った。「あなたは、わたしの批判にいつでも賛成する。我慢できないわ」
「でも、心からそう思ってるんです」僕はきっぱりと言った。「ほんとうです。あなたの写真に似たようなことかも知らない。引伸ばすと、コンテクストが本物でなくなる。なにごとも距離をおいて見なくてはいけない。抜粋集にはご用心。」
(p.151)
言うまでもないが、ラストの着地のさせ方も本当に素晴らしい。語りすぎず、それでいて目を覚まさせるような結末には、海外文学ファンのみならず、国内ミステリファンにも納得してもらえるんじゃなかろうか。
うっとりしすぎてため息ばかり出てしまう
恥ずかしながらこの本で初めて須賀敦子さんの訳に触れたのだが、ため息の連続で、タブッキの他の著作はもちろんのこと、須賀敦子さん自身の書かれた著作も読まなくちゃいけない(良くないのだが、私はある種読書に対して強迫観念じみたところがある)と強く思った次第。
本作はとても短いし、さらりと読めるのに何度でも味わえてその度にうっとり・にやにやできて、異国に思いを馳せ、ラストで最高に興奮できるお得感満載の本。
ぜひあなたの鞄に、トイレに、台所の紅茶棚の脇に、ベランダにどうぞ。めくるたびにめくるめくインドの旅。

- 作者: アントニオタブッキ,Antonio Tabucchi,須賀敦子
- 出版社/メーカー: 白水社
- 発売日: 1993/10/01
- メディア: 新書
- 購入: 9人 クリック: 44回
- この商品を含むブログ (75件) を見る