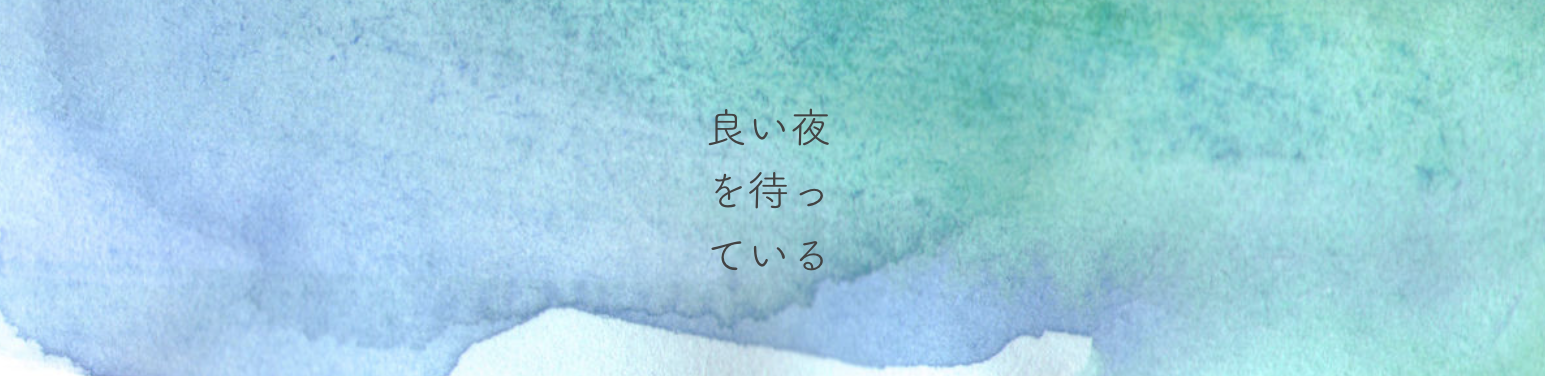![[レベッカ・ソルニット, ハーン小路恭子]の説教したがる男たち](https://m.media-amazon.com/images/I/417FvcQqnTL.jpg)
レベッカの著作を読むのは2作目。1冊目は『それを、真の名で呼ぶならば』というトランプ政権の痛烈な批判から環境問題、そしてベースにあるフェミニズムまで幅広いテーマのエッセイ集。こちらもとても興味深かったけれど、よりフェミニズムに焦点を当てた本作のほうが私は好きかな。
「マンスプレイニング」という言葉を初めて知ったのは、ツイッターだった。
その言葉とともに多分この本がTLに流れてきていて、積んでいたのをようやく読んだ。彼女が「マンスプレイニング」の発語者では無いらしいけれど、まさしくマンスプ案件と言える、痛快なお話から始まる。
始まりは軽妙な印象だけれど、データに基づいて、いかにこの世界で女がレイプされ、殺され続けているか、そのからくりを解きほぐしていく。彼女の筆致は、とても読みやすくてまさしく歩くようなテンポで(『ウォークス 歩くことの精神史』という著作もあるから、多分、彼女は歩きながら考える人なのだ)語りかけてくれる。
合衆国では6.2分に1度、レイプが起きている。
この中では報告されないものも無数にあるだろうから、実際はもっと多いだろう。
ジェンダーギャップ指数が低すぎて恥ずかしすぎる日本(2020年、順位は153か国中121位)では、女性たちが口をつぐまざるを得ない事件がもっともっとあるかもしれない。
このことを考えると気が滅入って仕方がない。コロナ禍での政府の対応を見ていても感じるが、恥の概念はもう、この国にはないのかもしれない。
女性の解放はしばしば男性の領域を侵犯し、権力と特権を奪うことを意図した運動として描かれてきたけれど、それはまるで暗澹たるゼロサム・ゲームのようなもので、一度にひとつのジェンダーだけが自由でパワフルになれると言っているようなものだった。でもみんなで自由になるか、みんなで奴隷になるか、ふたつにひとつだ。もちろん他人に勝ち、支配し、罰を与え、至高の存在としてあらねば気が済まないような者の心理はおそろしく、自由とはほど遠い。だが、達成できもしない目標を追い求めるのをやめさえすれば、みんな解放されるのだ。
(「長すぎる戦い」p.47-48)
私は他の人がどのジェンダーを好もうが本当にどうでもよくて、自分自身はなんとなく異性愛者としてやってきているけれど、別にそれがいつ変わっても変わらなくてもどうでもいい。なぜ他人の性愛や性的指向に口出しする気になれるのか心底わからない。口出ししたところで何か得があるのか。他人が好きな人間と幸せに暮す、ただそれだけの権利を、未だにぐずぐず社会が認めたがらないのは本当にダサいなと思う。別にどのジェンダーを好こうが、一生独身でいようが、子供を産まなかろうが、社会が壊れてしまうわけではないのに。でも壊れてしまうと、思ってしまう構造なんだろう。「みんなで自由になる」ことがどうしても許せない人間もいる。その軛を解くために、みんなで自由になるために、あとどれくらい戦えばいいのか。この呪いはいつかは解けるんだろうか。
多分、この問いに答えは出ない。今はまだ。でももがき続けるのをやめたら、ここまで道を作ってくれた女性たちに、理解ある男性たちに、どちらの性でもない人々に、申し訳ないし、もがき続けるしかない、と思っている。本当に苦しくて、この戦いから降りたいと何度も思うが、女性としての性自認を持った私は、それだけで兵士にならざるを得ない。生理用品すら満足に手に入れられない女性たちがいる、この国で。
本書ではヴァージニア・ウルフについての章があって、私はその章がいっとう好きだ。
ウルフは自己を無理やり統一させる必要はない、もっと解放できると、あらゆる他者になることもできると、言ってくれている。それは彼女の著作を読めば肌で感じることができるが、こうやってレベッカが言語化してくれることで、もっともっと、彼女の著作を抱きしめたくなる。
複数であること、単純化できないこと、そしておそらくは謎に対するこだわりにおいて、ウルフはそのような自己を称え、拡大し、要請しているのだ。謎とは変成し続け、限界を超え、境界を持たず、もっとたくさんのものになろうとする力にほかならないのだから。
(「ウルフの闇」p.116)
その芸術がはらむ謎に敬意を払うこと。謎から広がる拡張性に思いを馳せること。問い続けること。対話をやめないこと。これは、今まで読んできたウルフを始めとしたフェミニズム関連の著作からいつも学び直す事柄だ。大学生の頃、一番最初にフェミニズムというものを知るきっかけとなったアドリエンヌ・リッチの詩を読んだときから。トリン・T・ミンハに出会った頃から、ずっと。
ウルフは私たちに果てしなさを与えてくれた。掴むことができないのに、抱きしめようとせずにはいられないような、水のように流れ、欲望のように止まることのない果てしなさを。道に迷うためのコンパスを。
(「ウルフの闇」p.125)
私にとって本は、芸術は、道に迷うためのコンパスなのだと、レベッカの言葉で思い知った。
どこに行くかもわからないし、どこへ行ってもいい。どこへだって行ける。
フェミニズムも変化し続けるだろう。今まで北を指していたコンパスが南を指すようになるかもしれない。
でもそれは、森の中で遭難することじゃなくて、行く先が広がった、ということにもなるのではないだろうか。
どうかその先で、女たちにも名前が与えられますように。ワールド・ワイド・ウェブから、ハッシュタグから広がる世界も、その足がかりとなってきているはずだ。
だからまだ、辛いけれど、諦めきれない。
巣を紡ぎつつ、そのうちにとらわれないこと。世界を、自分の人生を創造し、運命を自ら決めること。父のみならず祖母たちにも名を与え、まっすぐな線だけでなく網もたぐり寄せること。片づけるだけでなくもの作りもして、沈黙に追い込まれずに歌えること。ヴェールをはぎ取り、姿を現すこと。
(「グランドマザー・スパイダー」p.96)