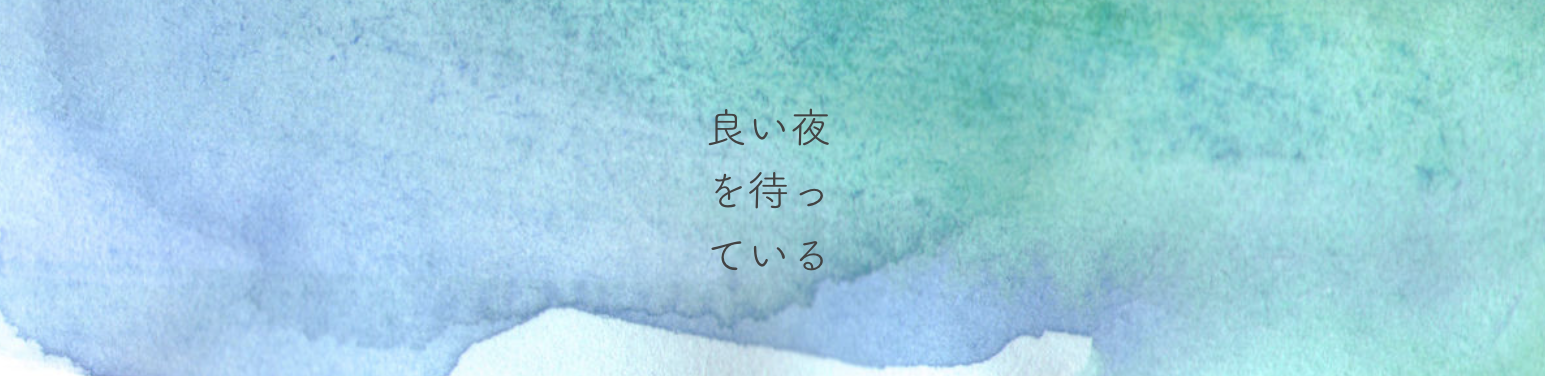この詩集は天気が悪い。
雨が降っていたり、雪が積もっていたり、なんとなくの曇天。それなのにふしぎと湿度がほとんどない。乾いていて、温度も低い。
その乾いた質感からか、夏のような、じくじくしたナマモノへの厭わしさを感じる。
死んだ夏をホルマリンに漬けて保存しておく。思い出をたくさん食べているから、今年の夏もぶくぶく太っていて気持ちわるい。裂けた脇腹からは花火が、海が、溜まった宿題がはみ出している。夏の死顔はいつも、いつも少しだけ欠けていて、どこかしら不潔だ。九月になっても夏の、吐気だけは残りつづける。p.18
熟れ、生殖し、腐り、膿んでいくような夏の「吐気」が残る「あの」感じ。
夏があまり好きではない(好きだけれども大手を振ってそれを是としない)人にはこの詩はとても実感を伴うものであろう。
そして夜。ひとり夜道を歩く、空を見上げて電線を視覚に絡めとり、俯いて猫を探す。
この一冊を貫いているのは孤独、それはとても鋭いけれど尖ったナイフではなくて、ピアノ線や、鉄製のフェンスのような、なにか線状のものを想起させる。とても繊細で、それ自体が切断されてしまう恐れがあるような、鋭利な線。
ぼくのなかには
だれも亡命させない
「種子」p.65
詩人というのは私たちが通り過ぎるものを凝視する。見続けると気が狂うことも厭わずに。
ぼくが
歩くのは辿りつくためじゃないから
(…)
どこにも到達しない
しかし それがぼくの望み
ぼくの在り方だった
「密室空間」p.62
辿り着くことを目的としない、それはたしかにひとつの詩人としての在り方だろう。
ここでの詩人は岩倉を指さない、概念としての詩人だ、だから心に詩を持つひとすべてのことだ。
「留まることは、走り続けるより困難だ」と言う詩人に若さゆえの体力を感じて少し脱力してしまうが、この詩集のことばたちは日々肩を落としてひとり生きる人間に、人間たちに、寄り添いはしないが少し離れた場所で、「僕もそうだよ」と言ってくれるような気がした。