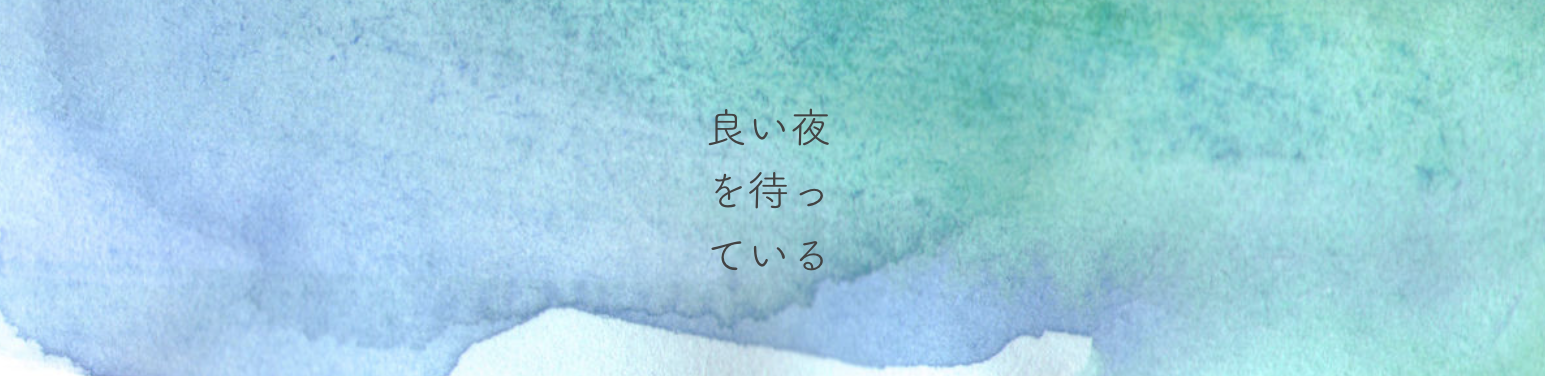毎日何かしらの活字を読んでいるが、詩となると毎日の摂取は (私にとっては) なかなか難しくて、その理由として「詩の大量摂取は胃もたれを起こす」からである。
この「胃もたれ」は濃厚かつ重厚かつ難解な (内容的にも、物理的にも) 小説なり評論なりを読んでいるときも比較的起こりやすいが、例えるなら小説や評論は翌日の午前中まで引きずってはいるものの、きちんと水分を摂って排出していけば昼頃には楽になれる二日酔いで、詩は翌日まる一日ベッドで唸っているはめになる二日酔いだ。
詩を読むことで、体力と精神力をかなり消費してしまうのだ。
小説・評論は「筋」や「論旨」が基本的にはあり (ほぼ筋がない散文詩のような小説もあるが) 道筋が見えやすい。比較的受動的な読みでも、それらのガイドのおかげで走り抜くことができる。途中、道に迷っても周辺の事情から察することもできる。登場人物を忘れても、読み直せば思い出せる。ガイドはト書きであり、論文構成であり、台詞でもあるが、間隔は不定としても必ずひとつ以上はその作品の中に見つけることができるし、それを視界の縁に捉えるだけで先に進めることが多い。
ところが一方、詩となるとそうはいかない。詩のことばはそこらに散らばって (纏まりがないという意味ではない) 私に拾い上げられるのを待っている。私が自ら腰を屈めてそれらを手にとり、ためすがめつしなければ、それらは何も示してはくれない。周りを見渡してもことばが在るだけで、その繋がりはやはり私自身がそれらを凝視し、または目を瞑り、手触りや味を確かめるしかない。捕まえたと思ったらするりと指の間から抜け落ちる。遠くにぼんやりと霞むことばに追いつきたくて走り続けても、雲の中を走るようでどこにも辿り着かず、途方にくれることもある。触っているうちに硬かったことばがぐんにゃりと形を変えることもある。
小説や評論に比べて、詩は、ことばの形が流動的なのだ。だから読み返したときにはもうその形はなぞれなかったり、そこにはなかったりする。小説や評論は、あいだに流動的なことばがあったとしても、ガイドはそこから動かず立ってくれていて、ある程度こちらの認識を一定のかたちで保つことができる。
「読み」における運動量がかなり多いせいで、詩を読むのはとても疲れる。
腰を屈めてことばを見つめ、ことばの裏をひっくり返し、指先で形をなぞり、匂いを嗅ぎ、舌先で舐め、引き寄せたら500m先まで逃げられ、追いついたらまた最初から、五感フルスロットルでことばを確かめていくしかない。
ただし、評論といっても哲学は (少なくとも私にとっては) 別物だ。初心者向けの解説書ではない哲学書は、それらを「読む」という行為において詩のそれと見分けがつかない。
また、精神力の面でもかなり消耗してしまう。
そもそも詩人というものは、ふだん私達が見過ごしたり、あるいは全く見えていなかったり、あえて見ないようにしていたりするものを凝視し、それらをことばにして私達に並べて見せてくれる人たちだ。それらを見つめ続けるとどうなるか。答えは簡単、狂ってしまう。
一般的な医学的意味合いとしての「狂人」とはまた別の、「自ら狂いに行く」類の人間なのだ、詩人というものは。ここで言う「詩人」は職業詩人だけを指さない。詩を読む人、詩に触れたことのある人、詩に取り憑かれている人、心に詩をもつすべての人のことだ。もちろんそこには、私も含まれている。詩を読むとき、程度の差はあれ、私達は狂気の際に居る。「ここから先に進んだら戻ってこれない」ギリギリのところまで行かないと、詩は掴めないことが多いからだ。
だから、詩を読んで、狂いに行ったとして、そこから帰ってくるのも一苦労なのだ。
それでも私は詩を読んでしまう。
これほどまでに満身創痍になる文学があるだろうか。ぐったりしてベッドに横たわってしまっても、その疲労はあまりにも甘美な疲労なのである。
だからやめられない。どんなにその道程が険しくても、結局ほとんど何も掴めなくても、どうしても読みたくなってしまう。そんな魔の中毒性が、詩にはあるのだ。