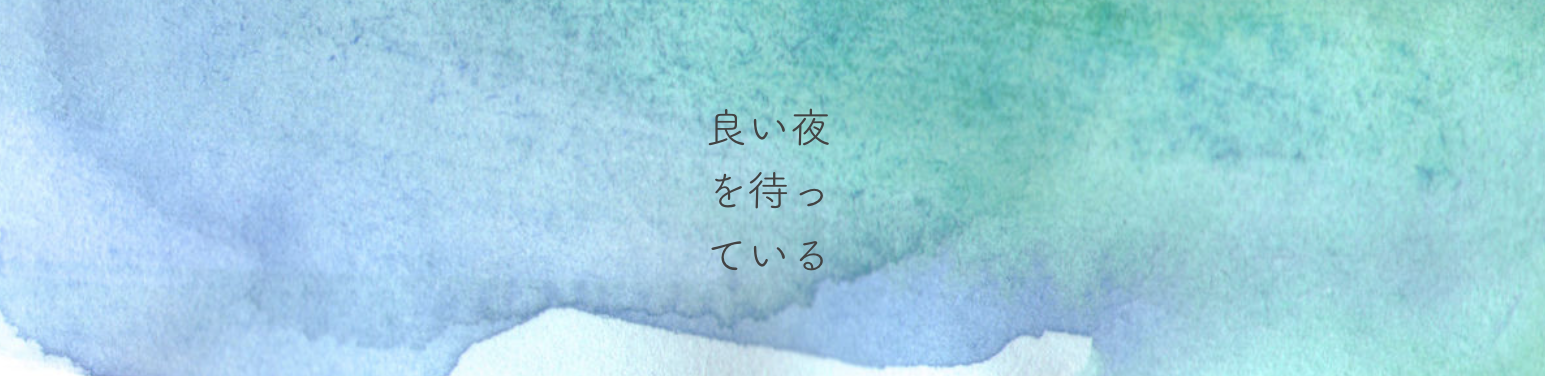愛すべきダメ男ものがたり
ダメ男ブンガクは数多くあれど、(私が好きなものだとラウリー『火山の下』、パワーズ『オルフェオ』など)『紙の民』はとことんダメ男の情けなさを物語、いや、物語を越えてこちら側にはみ出してくる形で楽しませてくれる小説だ。
この本の装丁やパラパラめくったときに時折現れるイラストや黒塗りの部分、ハチャメチャ(に見える)段組から、とっつきづらそうな印象を持たれてしまうかもしれないが、読んでみるとまったくそんなことはなく、寧ろとても親切設計で読みやすい。そしてこのお話の主題のひとつが「女に振られた。つらい」という、なんだかちょっと情けなさすぎる気がするものなのだが、その主題を物語が取り巻いていき、登場人物、作者、そして読者の枠を破壊し展開し、ただの情けないダメ男ものがたりでは終わらない。
土星VS登場人物
紙で作られた伝説の女性メルセド・デ・パペル、寝床でおもらしをし続けたせいで(と本人は思っている)妻に出て行かれてしまったフェデリコ・デ・ラ・フェ、その娘リトル・メルセド、プロレス界の英雄であり聖人でもあるサントス、全知の赤ん坊ベビー・ノストラダムス、街のギャングたち、メキシコ生まれという設定のリタ・ヘイワース、その他にもたくさんの登場人物がこの本には出てくる。そのすべてが実に魅力的で、彼ら個々人のストーリーが平行して語られていくのがこの本のひとつの特徴。段組が増えたり減ったりするのは彼らの視点ごとに段落が分けられているため。だからこの本は前述したとおり同時に複数の視点を楽しめるし混乱もあまりない、とても親切設計なのだ。
主人公のひとり、フェデリコ・デ・ラ・フェはあるとき「誰かに自分たちの生活や思考が監視されている」と気付き、その正体が「土星」(=著者であるプラセンシア)であり、土星と闘い生活を守らねばらないと街のギャングたちを先導し、どうにか土星の目を逃れようとしていく。彼らは鉛で家を覆い、思考を読まれてしまうときは物語のネタにもならないような単純なことしか考えないようにして土星と戦っていき、しまいには失恋でグズグズしている土星を本の余白へ追い込んでいく・・・というのがもうひとつの筋なのだが、他にも個々のエピソードが沢山あって、それらがどれもとてもチャーミング。
私がいちばん好きなエピソードは、「紙で作られた民」であるところのメルセド・デ・パペルの話。彼女はたくさんの男と寝る要するにビッチなのだが、男たちは彼女と寝ることでできてしまった切り傷を誇りに思い、ロサンゼルスの街中で舌にできた傷を見せ合う。そして読者もその仲間に加わっていく。一方メルセド・デ・パペルは実にあっさりしており、それがなんとも切ない。
彼は読者たちが思い思いにこの本を持つ方法も知っていた。開いた表紙を抱くようにして持つ者もいれば、本をテーブルに置き、ページをめくる前にはいつも指を舐め、唾液が余白に染み込む者もいた。
そしてほかにも、ひとりでいるときに本を開いてページの縁を舐め、自分たちもメルセド・デ・パペルに顔を埋めているのだと想像する読者もいた。彼らの血は溜まり、背表紙の溝を流れていった。紙と関係を結んだこれらの読者たちは、唇を舐めつつ外に出ていき、自分たちの傷やひりひりする舌を見せびらかし、メルセド・デ・パペルの恋人に加わった。
メルセド・デ・パペルが永遠の愛を信じることはなかった。一つの季節にわたって続くロマンスすら、彼女にとっては不可能で馬鹿げたことであった。
「燃えて、灰になって消えるものなのよ」と彼女は言い、床を掃いて新聞紙の切れ端をちり取りに押し込んだ。
土星も、登場人物たちも、そして読者も、紙によって傷つき、身体からインクを流し、愛する人にはインクをつけていく。紙が燃えて、いずれは灰となって消えてしまうことを知っていても。
ラストに向かっていく流れではとにかく土星が情けなくて笑ってしまうのだが(私生活の何もかもを小説に書いてしまうせいで恋人に愛想をつかされ、意気消沈し、登場人物が訪ねてきても、もういいよ、とぐったりしてベッドに向かってしまう)、どうしても憎めない。それは土星の情けなさゆえの優しさや、彼をとりまく傷だらけの登場人物たちの、どこか抜けていて愛らしいところが垣間見えるからだ。
土星は巨人であり、惑星のなかでも突出していたが、同時に彼は、台所の戸棚の上の扉を開けるためにスツールの上の立つ小柄な男でもあった。木箱に立って、彼女とキスしている夢想に耽る男。だが、戦争の司令官とはみなそのようなものである。傷心を抱えた、小柄な男たち。
紙の民たち
プラセンシアは三年かけてマルケスの『百年の孤独』を読み続けたということもあって、個々のエピソードの完成度もさることながら、それらを収束させていく手腕にも長けていて飽きさせない。物語の最後の台詞は、途中に登場人物によってバラされているにかかわらず(!)じんわりと染みてくる良さがある。
そして、物語を越えてフェデリコ・デ・ラ・フェたちの生活も続いてゆく。どうか、彼らが幸せであるようにと祈らずにはいられない。
本が好きな私達はみな紙の民で、これからも目からインクを流しながら、心にインクを染み込ませながら読んでいくのだろう。
そして、この物語から学んだことがあるとすれば、それは紙には用心せよということだった――紙の脆い作りと鋭い端に用心すること、ただし、もっぱらその上に書かれていることに気をつけること。