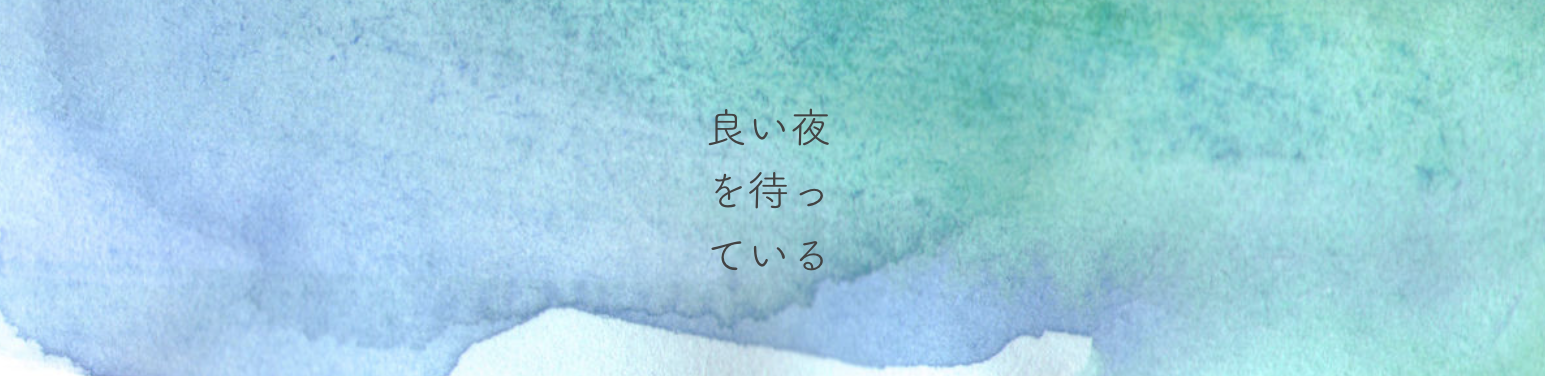イタリアの鬼才、トンマーゾ・ランドルフィの短編集。奇想天外なお話、どれも質感が違っていてバリエーション豊かで面白かった!
その中でも「カタチがないものに別の特性を付与する」作品が私は好きだな。
「『通俗歌唱法教本』より」は人間が喉から発する音には五官すべてによって鑑賞可能な特性があるというお話。低音歌手が発する中音声部の「ド」は140トンだそうだ。だからなるべく頭上より高く発するようにしないと、悲劇的なことになる(笑)。
味覚に関して言うと、音はたいがい苦いそうだ。具体的に言うとゲロ味。
事実、大概は、とりわけ高い音やきわめて低い音(すなわち最も苦い音である。その苦さに慣れることのできる歌手はどうやらごくわずかしかいないようである)を発する際に圧倒的になる渋面や努力については誰もが識っているところである。同様にまた、時として軽やかな声のソプラノ歌手が、彼女自身にとっても恐らく思いがけず甘く感じられた音を舌先で味わっているらしい光景も、皆の目撃しているはずのものである。
(p.138)
「騒ぎ立てる言葉たち」では歯磨き中、口をすすいでペッと吐き出した瞬間、言葉たちが飛び出してきてぴょんぴょん跳ね、口々に自分の言葉の持つ意味が気に食わない、「意味を再分配しろ」と文句を言う。自分のシニフィアンに合った(と言葉たちが思っている)シニフィエをくれということなんだろうか。このちっちゃな言葉たちがキィキィ騒ぎ立てているさまがなんだか、かしましくてかわいい。指で摘まれて瓶に押し込まれるあたりも古いディズニーアニメみたい。
表題作「カフカの父親」と「ゴーゴリの妻」は文豪たちの家族をこんなにおもちゃにしていいの?怒られない?と思うくらいハチャメチャな設定。だってカフカのお父さんは蜘蛛の胴体の部分が顔になっていて、埃だらけの納屋をカサカサ歩いたりするし、ゴーゴリの妻はビニール製のダッチワイフだし。ちなみに空気を入れる穴は肛門にある。
「ゴキブリの海」はタイトルがタイトルだけに脳内映像化スイッチを切って読んだのだけど、意外とゴキブリは弱っちくて、量が多いだけでそんなに獰猛じゃなくてホッとした(?)。それよりも登場人物たちがイッちゃっててそっちのほうが面白かった。ヒロイン役の女の子なんか、ちょっと用足しますとか言って突然おっぱい出して母乳を海に放り出したり蛆虫と交歓したりするんだもん。フロイト先生もビックリだ。
「ころころ」は殺人犯が犯行を自殺にみせかけるために凶器を被害者の右手に持たせるか左手に持たせるかで逡巡する10分間の話。この2つの選択肢をめぐってどんどん哲学の森に迷い込むさまが滑稽で、でもすこし物哀しくて味わい深い。
こんなに奇想天外なのに、結構気難しい文体も織り交ぜられてて、そこが設定の突拍子のなさを引き立てている気がするので、やっぱギャグは険しめの真顔で言わなきゃだめだなと思った。
私もダジャレ大好き人間だけど(老害っぽいなこれ)ランドルフィを見習って精進したい。