
タブッキは水彩画みたいだ、と読むたびに思う。
はっきりとした輪郭はないのに、離れて見るとちゃんと全体像が浮かび上がって見えてくるところとか、ぼんやりしているようで、細部はハッとするほど鮮やかだったりするところが、よく似ている。
ペレイラはうだつの上がらない、太っちょの新聞記者。妻を亡くしてからはひとりで暮らしている。妻の写真と話すのが日常の癒やしとなっていて、毎日毎日、砂糖をもりもり入れたレモネードを10杯飲み(だから医者に怒られる)、オムレツを食べている。新聞の文芸面を任されることになり、ひょんなことからモンテイロ・ロッシという若者に出会い、文芸面の1コーナーを任せるべく、作家の追悼文を依頼する。
ペレイラが刮目したロッシの文章は、結局のところほとんど盗用だったし、実際に文章を書かせてみたら酷い出来だったのに、ペレイラは結局、ロッシの面倒を見てしまう。
もし私が20代前半でこの本を読んでいたら、ろくに働きもせずお金ばかりせびって、怪しい政治活動に手を染めているようなロッシのことを嫌っていただろう。仕事も無責任だし、ペレイラの優しさにつけ込んでいるようで。ペレイラもペレイラだ、なぜそんなロッシの世話を焼くのかとイライラしただろう。でも今なら、ロッシの面倒を見てしまうペレイラの気持ちが少しわかる気がする。若者の放つ独特のエネルギーの渦に巻き込まれることは、ときにとても心地よいものだ。そのエネルギーが自分の背中も押してくれるような気がして、心強く思えることがある。おお、若者よ、と達観したり諦観したり、説教することばかりが中年しぐさではない。若者たちの力強さは、そのベクトルが自分に向かっていなくても、誰かを勇気づけたりすることもあるのだ。
ペレイラの穏やかな日常は、ロッシと出会ってから徐々に変化する。独裁政権の不穏な足音が近づいてくる中で、自分の信条を貫くべく動き出したロッシの行動に巻き込まれ、ペレイラの静かな生活は破綻してゆく。けれどもペレイラは、それを避けようとしない。むしろ最後には、ロッシの放つエネルギーに鼓舞されるように、自ら動き出す。
「供述によるとペレイラは」という文章から紡ぎ出される物語は、否応なしに「供述させられる状況にある」ペレイラを想像させる。「供述」に至るまでにペレイラを襲った悲劇と、あまり明るくはないであろう彼の現在・未来が冒頭から約束されている。もやもやとした曇天のような不安に覆われながらも、どうして「供述」せざるを得なくなったのか、という謎を追いかけていくミステリー的な要素もあって、ページを繰る手が止まらなかった。このあたりは「遠い水平線」や「インド夜想曲」にも通じるところがある。
少しだけ希望が持てるのは、ペレイラが子供の頃の思い出や、見た夢などは「この事件には関係がない」と供述しないところ。大切にしている、宝物の記憶が、どうかそのまま、少しでも彼の心を温めていますように。
ペレイラは亡くなった妻の写真を鞄にしまうとき、息が苦しくないように写真を上向きにしてそっと仕舞う。この仕草の切なさが、「供述によると」の効果も相まって、胸を締め付ける。
ハッピーエンドでは決して無い小説だけれど、読後感は切なさと哀しさと、少しの欠片がきらめくような余韻があって、改めてタブッキは稀有な作家だなと思った。本当に大好きで、大切な作品になった。
私もいつか、リスボンで、ペレイラががぶ飲みしていたレモネードを飲んでみたい。オムレツも2個くらい食べちゃおう。そしてペレイラが愛した文学に、正義に、思いを馳せたりしてみたい。
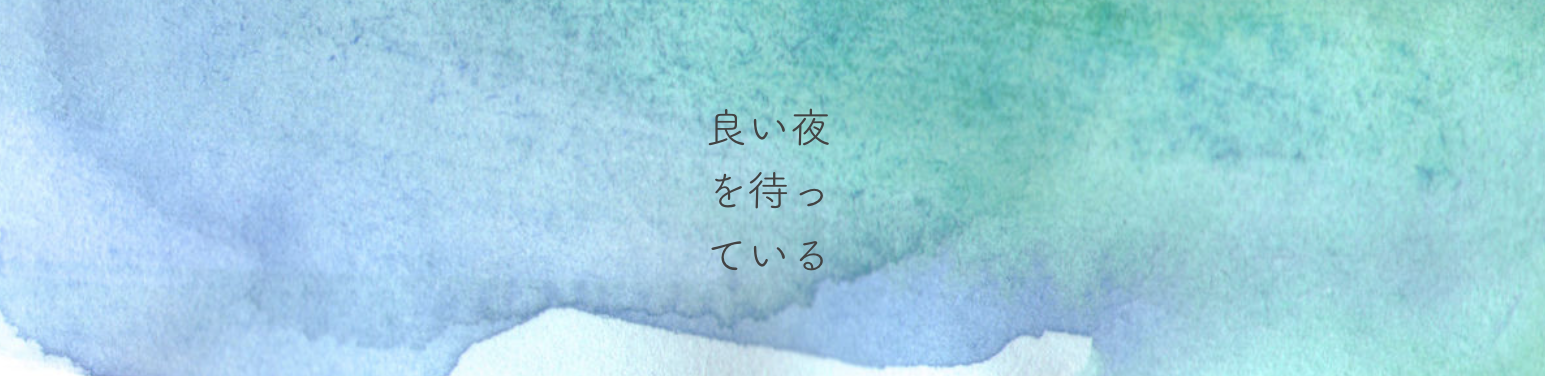






![[ドストエフスキー, 原 卓也]のカラマーゾフの兄弟(上)(新潮文庫)](https://m.media-amazon.com/images/I/51qgf+X4MZL.jpg)
![[ドストエフスキー, 原 卓也]のカラマーゾフの兄弟(中)(新潮文庫)](https://m.media-amazon.com/images/I/51FEbIO+APL.jpg)
![[ドストエフスキー, 原 卓也]のカラマーゾフの兄弟(下)(新潮文庫)](https://m.media-amazon.com/images/I/51oONZ7uQIL.jpg)



![[パトリシア・ハイスミス, 白石朗]の見知らぬ乗客 (河出文庫)](https://m.media-amazon.com/images/I/51ONy5FShhL.jpg)


